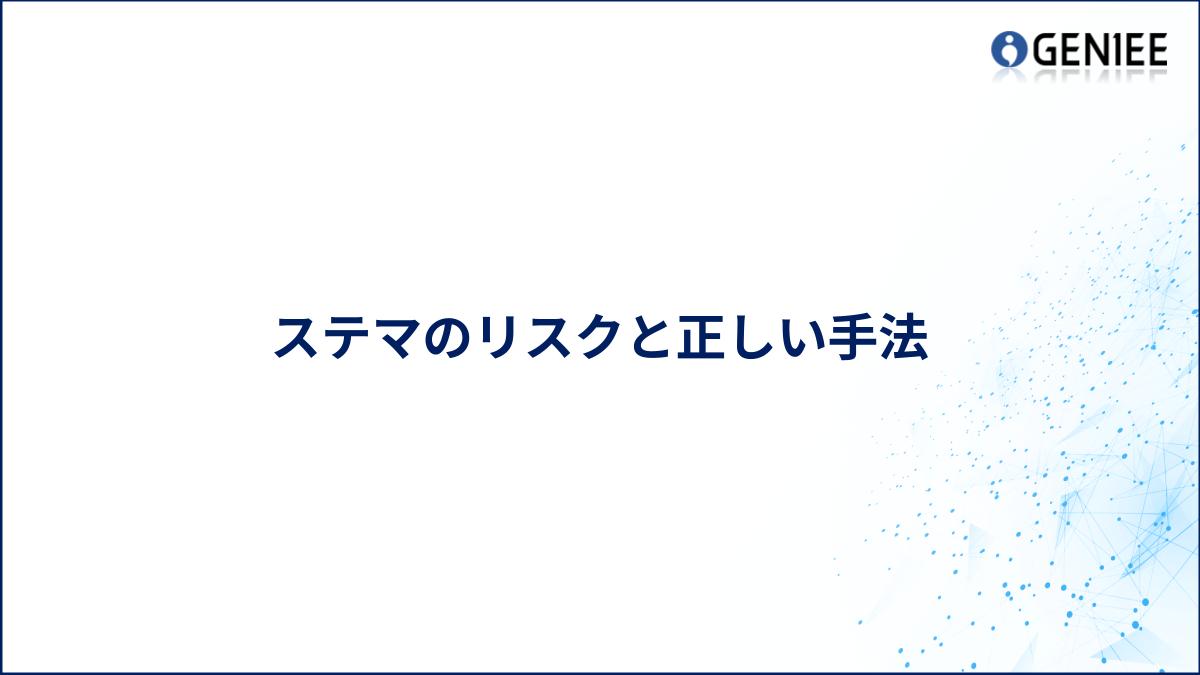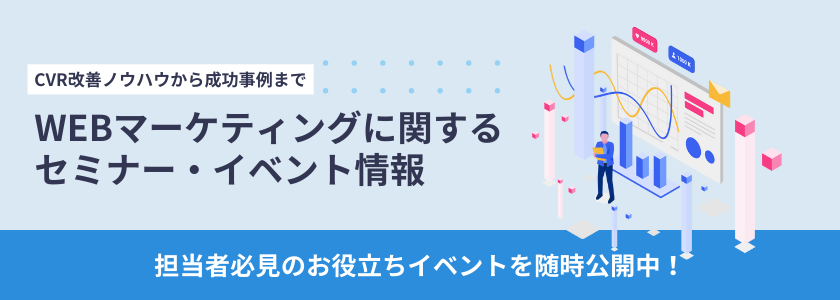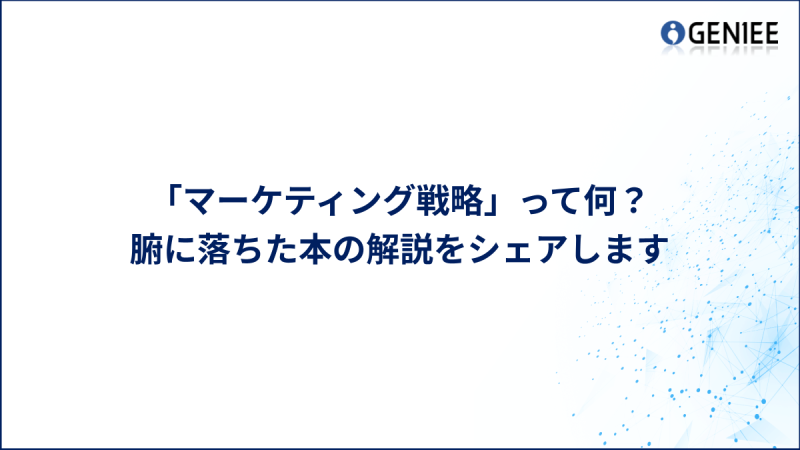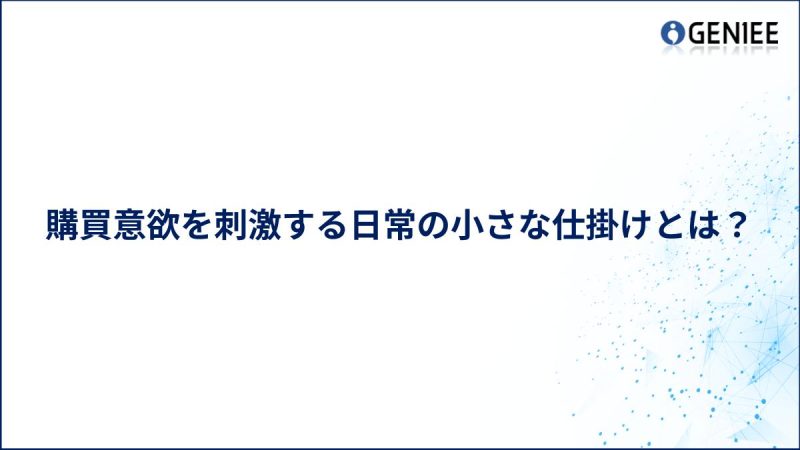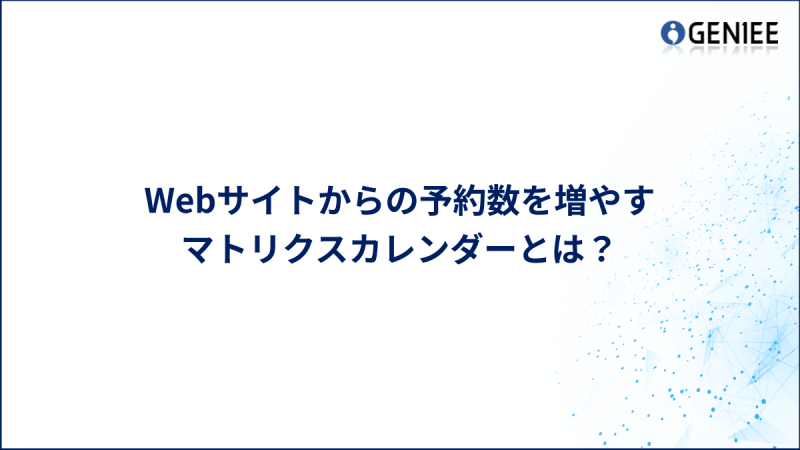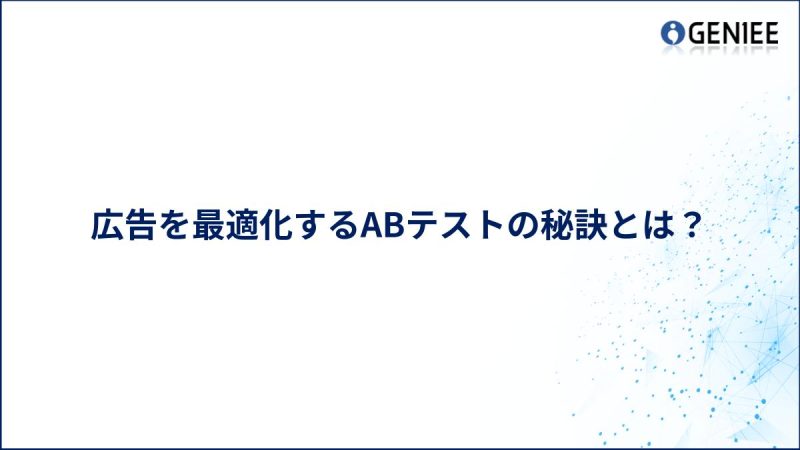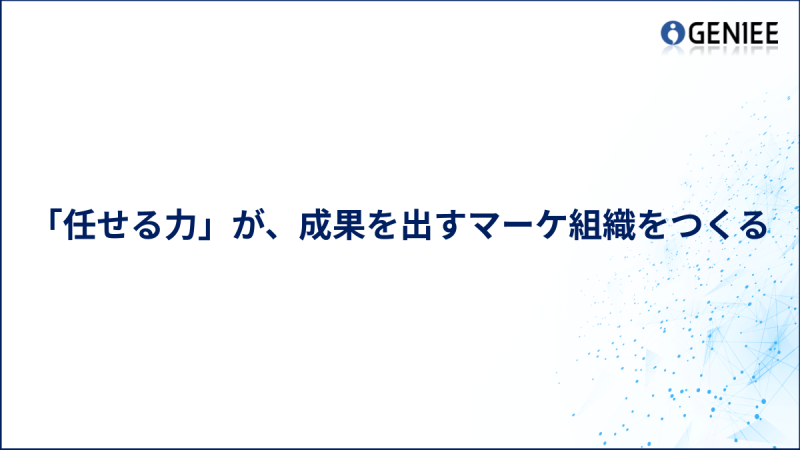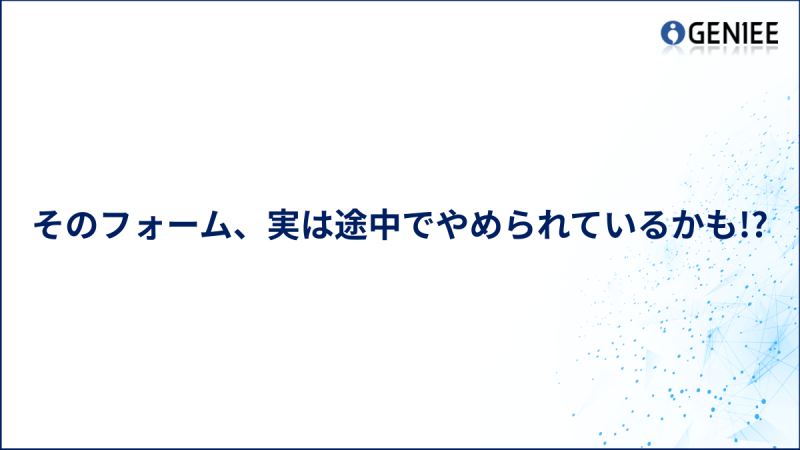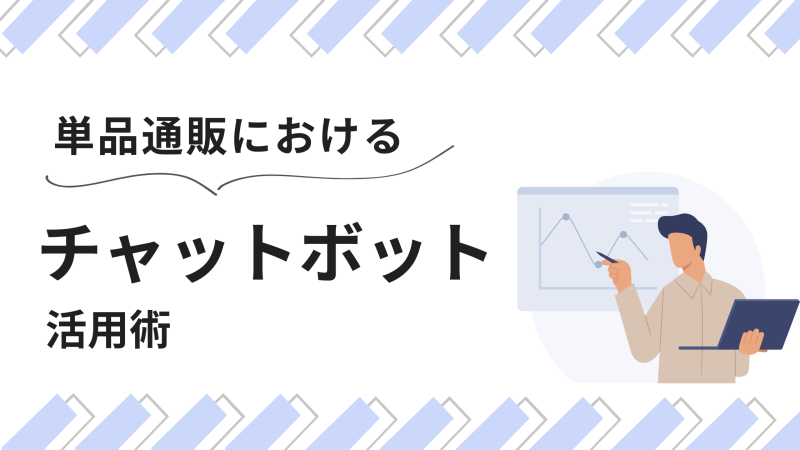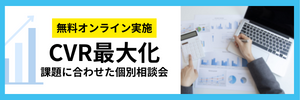以前、自社のSNSでインフルエンサーに商品を紹介してもらった際、「これ、すごくよかったです!」と好意的な投稿をしてくれたことがありました。
その時は、純粋にありがたい気持ちだったのですが、ふと気づいてしまったんです。
あれ?これって「PR」って記載しなくて良かったんだっけ?
当時は深く考えずにOKを出してしまいましたが、今振り返れば、完全にアウトな可能性も。
というのも、2023年10月からステマ規制がスタートし、「知らなかった」では済まされない時代だからです。
今回は、ステルスマーケティングにまつわるリスクとともに、マーケターが注意すべきポイントや、ステマを避ける方法を分かりやすくお伝えします。
そもそもステマって何?
ステマとは、簡単にいうと、「これ広告です」と言わずにこっそり宣伝しちゃう方法なんです。「ステルス(隠密)」という言葉の通り、消費者に広告であることをばれないように情報を届ける手法です。

放置していると危ない!ステマによるリスク
消費者の信頼喪失
ステマがバレた時の消費者の反応は想像以上に厳しいです。「騙された!」という感情は、一度芽生えると取返しがつきません。調査によると、ステマが発覚した企業からは78%もの人が「もう買いたくない」と思うそうです。
法的リスク
2023年10月からは、ステマは完全にアウト!景品表示法違反として規制対象となり、違反した場合は行政処分を受けるリスクがあります。違反企業には措置命令や課徴金納付命令などの厳しい処分が下される可能性があります。
ブランド価値の低下
ステマが発覚すると、SNSで批判の声はあっという間に広がり、長期間にわたって企業評価に影響します。そう考えると、一時的な宣伝効果なんて、リスクに見合わないですよね。
ステマのリスクを回避するためには?
PR案件であることを明示する
インフルエンサーに依頼する場合は必ず「#PR」「#タイアップ」などのタグを付けてもらいましょう。消費者庁のガイドラインでは、単に末尾に小さく記載するだけでなく、「一般消費者が認識できる方法」での表示が求められています。
社内ルールの整備
SNS運用に関する社内でのルール作りも大切です。特に以下の3点は必ずチェックしましょう!
- PR表記の具体的な方法の統一
社内マニュアルでルールを明文化しておきましょう。 - インフルエンサーとの契約書への明記
PR表記を怠った際の具体的な条項を入れておくと安心です。 - 投稿前のチェック体制の構築
法務部門を含めた複数人で確認する体制を整えましょう。
まとめ
ステマに頼らなくても、「ファンマーケティング」のように、透明性を大切にしたコミュニケーションと、本当に良い商品を作ることで、自然と口コミは広がります。
「隠す」より「正直に伝える」方が、長い目で見れば絶対にお得。これからのマーケティングは透明性こそが武器になります!