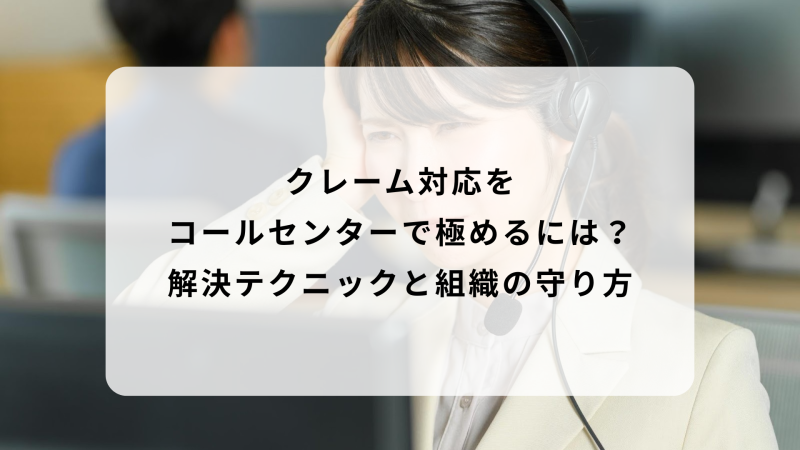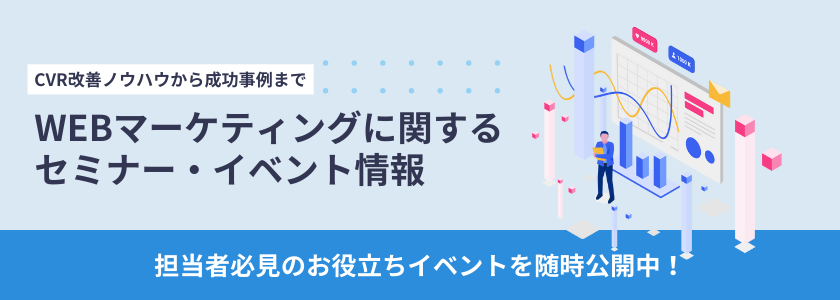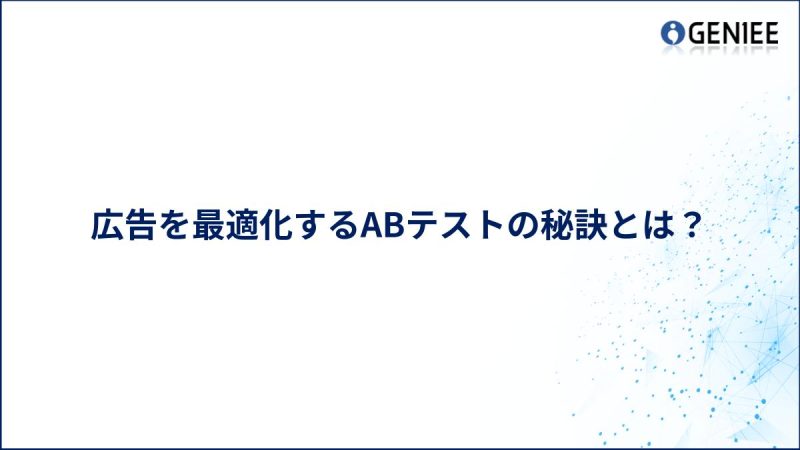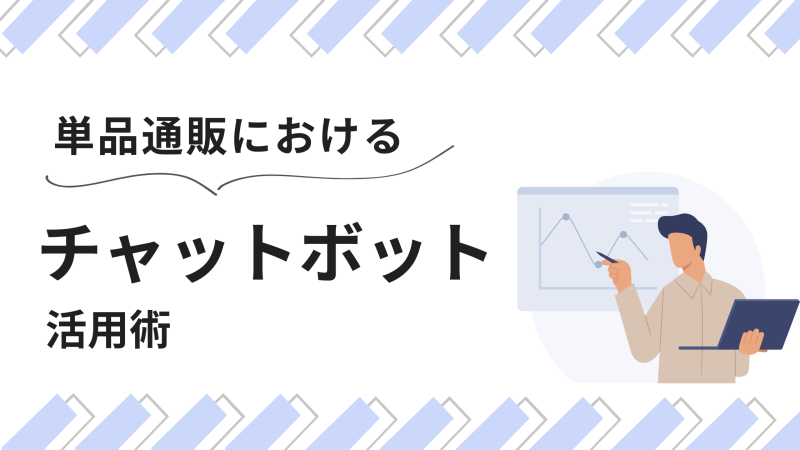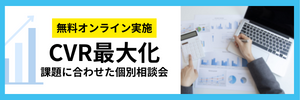「最近、サイトのコンバージョン率が下がっている…。」 「対策を打っているのに、なかなか改善が見られない…。」
このような悩みはWebマーケティング担当者の付き物ではないでしょうか?
この記事ではCVR低下の原因究明の考え方と、そのために活用できるツールを紹介します。
CVRにお悩みの方は是非参考にしてみてください。

目次
CVRとは?

訪問者が商品購入や資料請求などの目標行動を達成した割合を示す指標です。
CVR(コンバージョン率)=CV(コンバージョン数)÷サイトセッション数×100
CVRは「コンバージョン数 ÷ セッション数 × 100」で計算することができます。
CVRが高いということは、サイトの訪問者が興味を持ち、実際に行動を起こしていることを意味します。マーケティング効果を評価する際の重要な基準となります。

平均的なCVRは?
一般的に1~2%程度が目安とされることが多いです。
これは平均的な数値であり、商材の種類や販売チャネル、コンバージョンポイントによって大きく異なります。
例えば、消耗品のように購入のハードルが低い商材では比較的高いCVRが期待できます。一方で、車や不動産のような高額商品などは、購入に慎重になります。そのため、CVRが低くなる傾向があります。
また、無料トライアルや会員登録などは、ユーザーの心理的負担が少ない。そのため、商品購入に比べて高いCVRを示すことが一般的です。
CVRは広告の種類や流入経路、サイトの使いやすさなど、多くの要因によって左右されます。そのため、自社の状況に合わせて多角的に分析し、最適な改善施策を講じることが重要です。
CVRの低下を感じた時にまずやるべきことは?

・業界の一般的なCVRより自社が劣っている…
・目標としているCVRよりも数値がギャップしている…
・数カ月前よりもCVRが下がっている…
こんなことを感じた際にまずやるべきことは「データ分析による原因究明」です。
多くの企業は表面的な数値の変化だけを見て、安易な対策を実施してしまいます。「CTAボタンの色を変えれば改善するはず」「競合が安いから価格を下げよう!」といった、データに基づかない判断は、さらなる機会損失を招く可能性があります。
データ分析における指標

効果的なデータ分析を行うためには、適切な指標(KPI)の選定と測定が不可欠です。
ここでは、代表的な分析指標とその活用方法について解説します。
基本的なトラフィック指標
セッション数
セッション数の変動は、サイトの集客力を直接的に示す重要な指標です。
特に注目すべきは、前年同月比での推移や施策実施前後の変化です。セッション数が急激に減少している場合は、検索エンジンのアルゴリズム変更や技術的な問題が発生している可能性があります。
また、セッション数が増加していても、それが質の良いトラフィックかを確認することが重要です。特定の流入元からの急激な増加はスパムの可能性もあります。そのため、他の指標と併せてチェックしましょう。
ユーザー数
ユーザー数は、実際のサイト訪問者数を把握する基本的な指標です。
新規ユーザーとリピートユーザーの割合は、サイトの健全性を示す重要な要素となります。一般的に、新規ユーザーが40〜60%の範囲にあることが望ましいとされています。
新規ユーザーをきちんと集客できているかどうかも重要なポイントです。
直帰率
直帰率の上昇は、ユーザーの期待とコンテンツにミスマッチが生じている危険信号です。
特に広告経由での流入時には注意が必要です。広告内容とランディングページの整合性が取れないと、ユーザーは「求めていた情報と違う」と感じて離脱してしまいます。
クリエイティブやメタディスクリプションが適切に訴求できているかを確認しましょう。
目安として、直帰率が60%を超えている場合は、見直しを検討することをおすすめします。

ユーザー行動に関する指標
滞在時間
サイト全体や各ページごとの滞在時間は、ユーザーの興味や関心度を測る指標となります。
滞在時間が長いほど、そのコンテンツがユーザーのニーズに合致している可能性が高いと考えられます。逆に、滞在時間が短い場合は、ユーザーが求めている情報にたどり着けていない、またはコンテンツの質や分かりやすさに問題がある可能性があります。
特に商品やサービス詳細ページにおける滞在時間は、CVRに関わる重要なサインです。商品説明不足や、画像やスペック情報が不十分だと、ユーザーが離脱する可能性も上がります。
直近1ヶ月の滞在時間データを前月や前年同月と比較し、異常値がないか、確認しましょう。トレンドにあっているかなどを定期的にモニタリングを実施する仕組みが重要です。
ページビュー数
ページビュー数を分析することで、コンテンツの閲覧状況を把握することが出来ます。
1セッションあたりのページビュー数が2ページ以下の場合、サイトの回遊性に課題がある可能性があります。関連コンテンツの提案やナビゲーションの改善を検討しましょう。
人気コンテンツの特徴を分析し、他のページに活かすことで、サイト改善につながります。定期的なコンテンツ評価と更新が重要です。
クリック率(CTR)
クリック率は、ユーザーの興味関心度を可視化することが可能です。
CTRの目安として検索結果が、1位表示で20%以上、広告では1〜2%が一般的です。(業界やコンテンツの内容によって数字は異なります。)CTRが低い場合は、タイトルやメタディスクリプションの改善が効果的です。
サイト内のボタンやリンクのCTRが低い場合は、配置位置やデザイン、文言の見直しを検討しましょう。定期的なABテストによる改善が推奨されます。

ユーザー属性に関する指標
デバイス別データ
デバイス別データは、ユーザーの利用環境を把握する重要な指標です。
現在では、スマートフォンからのアクセスが70%以上を占めるケースが一般的です。デバイス別でコンバージョン率に大きな差がある場合は、特定のデバイスでの使いづらさが示唆されます。
レスポンシブ対応の評価では、各デバイスでの表示崩れやボタンの操作性などを定期的にチェックすることが重要です。
セグメント分析
セグメント分析は、ユーザー属性別の行動傾向を把握する高度な分析手法です。
年齢層や性別、地域などの属性別に行動パターンを分析することで、ターゲットに応じた効果的な施策立案が可能になります。
例えば、特定の年齢層での離脱率が高い場合、そのセグメントに向けたコンテンツやUIの改善を検討します。定期的なセグメント分析により、より精緻なマーケティング施策の実現が可能です。
データ分析に活用できるツール

効果的なデータ分析を実施するためには、目的に応じた適切なツールの選択が重要です。ここでは、代表的なデータ分析ツールとその特徴、活用方法についてご紹介します。
Google Analytics
Google Analyticsは、単なるアクセス解析ツールを超え、ユーザーの行動やコンバージョンプロセスを多角的に分析できる強力なプラットフォームです。
基本的なページビューやセッション数の把握に加え、GA4の「探索」機能を使えば、ユーザーがどのページからどのページへ遷移し、どの段階で離脱しているかを視覚的に把握できます。これにより、ユーザージャーニーのボトルネックを特定しやすくなります。
また、ユーザーセグメント別の分析では、新規ユーザーとリピーター、地域別、デバイス別など多様な切り口で行動を比較できます。さらに、カスタムイベントを設定すれば、動画の再生やフォーム送信など、特定のユーザーアクションを詳細に追跡し、より深いインサイトを得られます。リアルタイムレポートを活用すれば、キャンペーン開始直後の反応を即座に確認でき、迅速な対応が可能です。
GA4は、機械学習を用いた予測指標やユーザーライフサイクル分析も強化されており、将来のユーザー行動を予測し、先手を打った施策立案が可能です。これらの機能を駆使することで、単なる数値の羅列ではなく、ユーザーの心理や行動背景を理解し、具体的な改善策を導き出せます。
導入時には、トラッキングコードの正確な設置、目標設定の適切さ、フィルタリング設定など、基本設定の精度が重要です。これにより、信頼性の高いデータ収集が実現し、分析の質が向上します。
ヒートマップツール
ヒートマップツールは、ユーザーのウェブサイト上での具体的な行動を視覚的に把握できるツールで、クリックの集中箇所やスクロールの到達度、マウスの動きなどを色の濃淡で示します。これにより、ユーザーがどのコンテンツに注目し、どこで興味を失っているかを直感的に理解できます。
例えば、重要なCTAボタンがユーザーの視線やクリックから外れている場合、配置やデザインの見直しが必要と判断できます。さらに、セッションリプレイ機能を備えたツールでは、実際のユーザー操作を動画で再生でき、ユーザーがどのようにページを閲覧し、どのタイミングで迷ったり離脱したりしたかを詳細に分析可能です。こうした行動データは、定量的なアクセス解析だけでは見えにくいユーザー体験の質を改善するための重要な手がかりとなります。

関連記事
ヒートマップ分析で丸裸!仕組み・活用方法から導入時のポイントまで徹底解説
ヒートマップ分析の基本から活用方法、ツール選びのポイントまで、Webサイト改善を目指す方にとって役立つ情報を解説します。
A/Bテストツール
A/Bテストツールとは、ウェブサイトの2つのパターンを同時に公開し、どちらがより効果的なのか検証を可能にするツールです。
多くのツールではノーコードで編集が可能なため、エンジニア知識が乏しい場合でも、容易にテストを実施することが出来ます。また、レポート機能や分析機能を活用することで、スムーズにデータに基づいた判断を実現します。
ページのレイアウト、見出しの文言、CTAボタンの色や配置、画像の有無など、多様な要素を対象に、多変量テスト(MVT)を活用すれば、複数の要素を同時に検証し、より複雑な最適化ができるようになるでしょう。
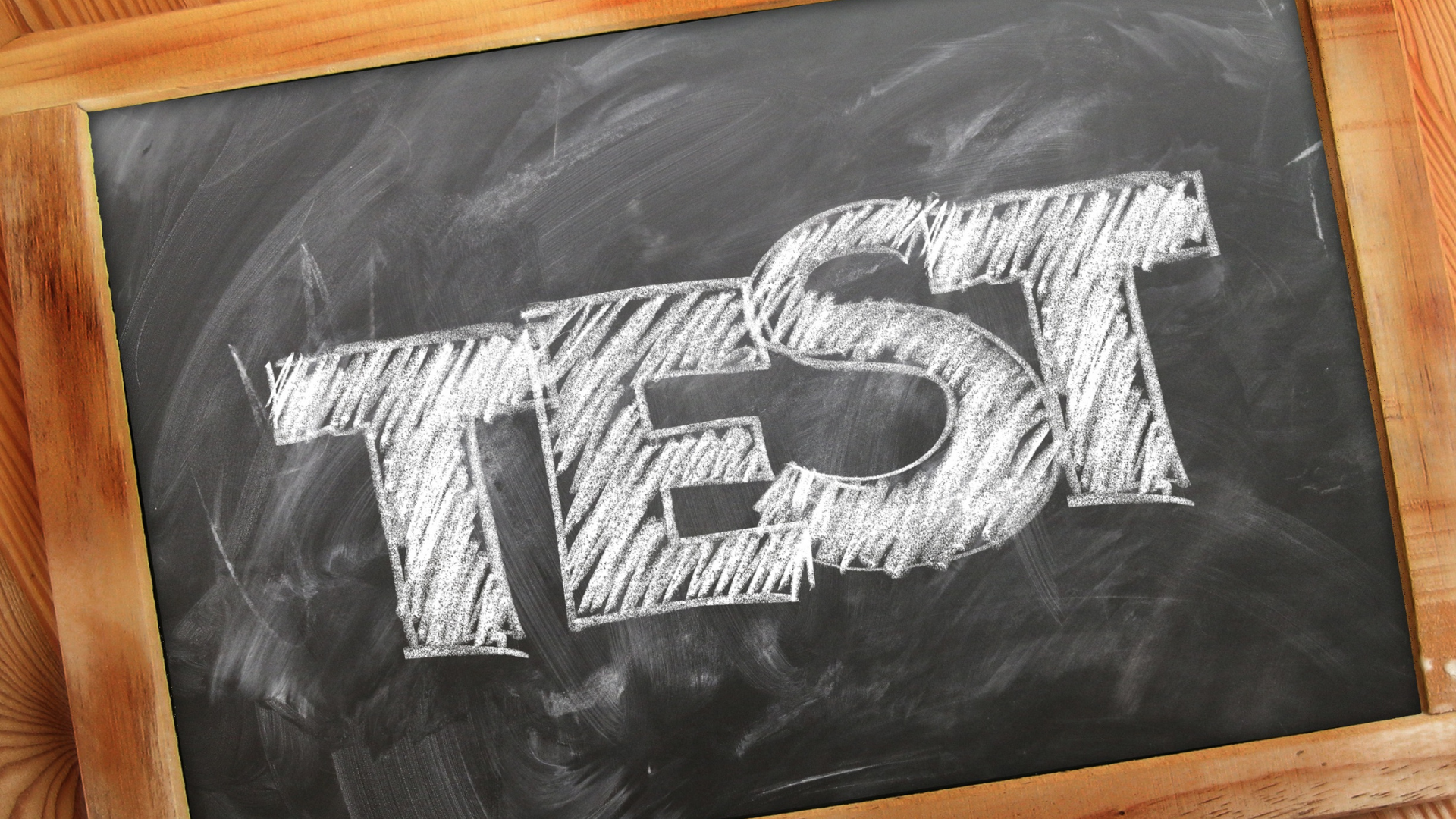
チャットボットを活用したCVR改善の事例

データ分析の結果、「しっかりをサイトに集客できているにも関わらずCVが獲得できていない!」という課題が見つかった場合、その原因は「入力フォーム」にあるかもしれません。
実は入力フォームページまで辿り着いても、ユーザーの半数は離脱すると言われています。
入力フォームでの離脱が多い原因下記の通りです。
- 入力項目が多すぎる
- 分かりにくい設計や表示
- スマートフォンなど特定デバイスでの操作性の悪さ
フォーム改善にはEFO(Entry Form Optimization)ツールやチャットボットの活用が有効です。ユーザーの入力をサポートし、離脱率の低減とCVR向上につなげることが可能です。
ここでは、チャットボットを活用してCVRを改善した事例を紹介します。
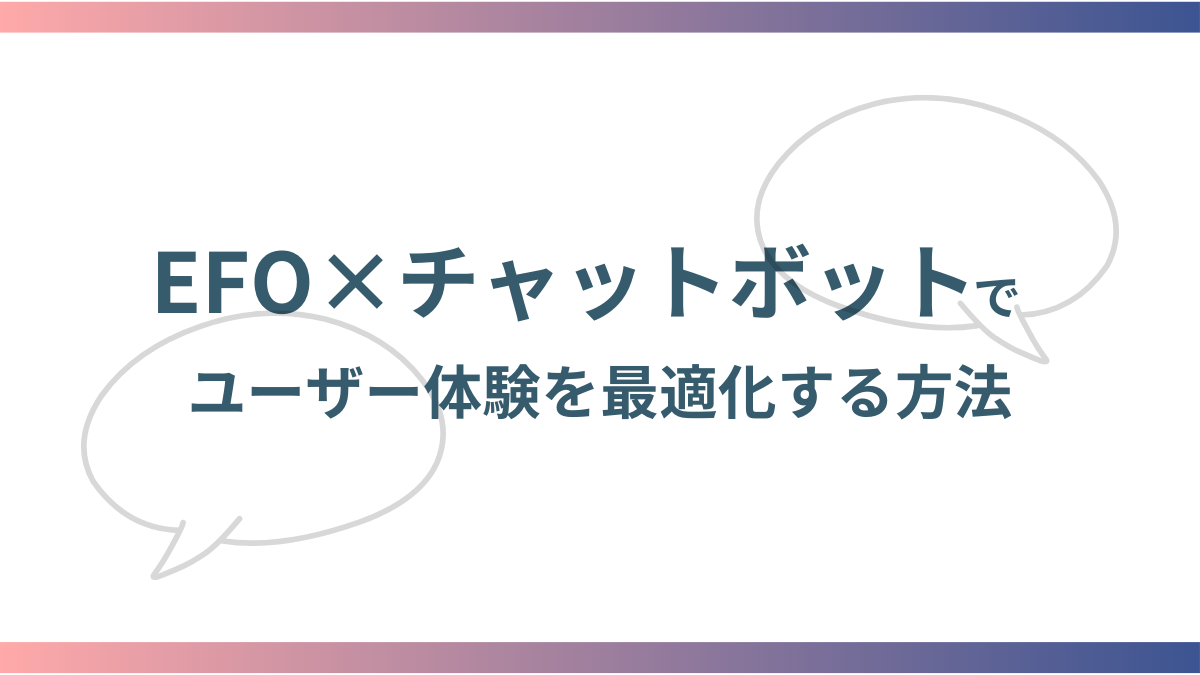
株式会社バルクオム様
株式会社バルクオムは、メンズスキンケアを中心にヘアケアやボディケア、インナーケアまで幅広く展開するブランドです。オンラインストアやECモール、全国のドラッグストアなどで商品を提供しています。
同社では入力フォームの手間や項目の多さによる離脱に課題を感じていました。そこで、チャットボット型EFOツール「GENIEE CHAT」を導入。
導入後は、チャットボットの設定変更やクリエイティブ差し替えの工数が大幅に削減され、作業時間を大幅に短縮。これにより、マーケティング施策の立案やクリエイティブ制作に注力できるようになりました。UX面でも改善が進み、特に入力項目の整理とCTAボタンのデザイン変更が効果的でした。結果的に、CVRは約1.5倍に向上しました。

まとめ
CVR低下を感じたら、まずはデータ分析による原因究明が重要です。
セッション数や直帰率、滞在時間、クリック率などの指標を多角的に確認しましょう。特に、デバイス別やセグメント分析を活用すると良いです。問題のある部分を特定しやすくなります。
データ分析には、Google Analyticsやヒートマップ、A/Bテストツールなどが有効です。これらを有効的に活用することで、ユーザーの動きを詳細に分析することが可能になります。仮説検証を繰り返し、データに基づいた施策を継続的に実施しましょう。
チャット型EFOツール「GENIEE CHAT」
株式会社ジーニーでは、入力フォームを改善し、コンバージョン率を向上させるための「GENIEE CHAT」を提供しています。
Webサイト上に設置している入力フォームをチャット型に置き換えることで、スムーズなフォーム入力が可能になり、その結果、フォーム離脱率を低減し、入力完了率の向上が期待できます。

関連記事
-

-

-
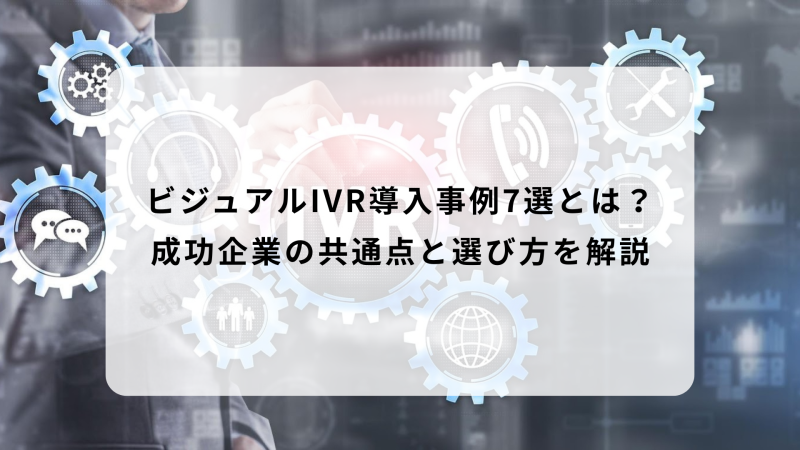
-

-
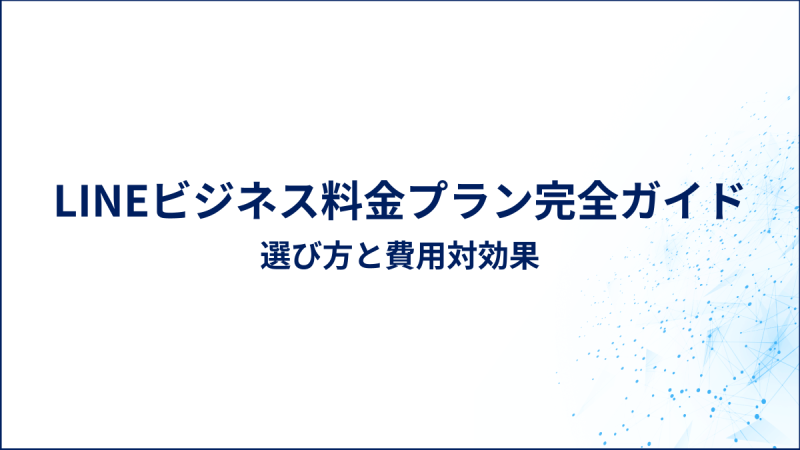
-
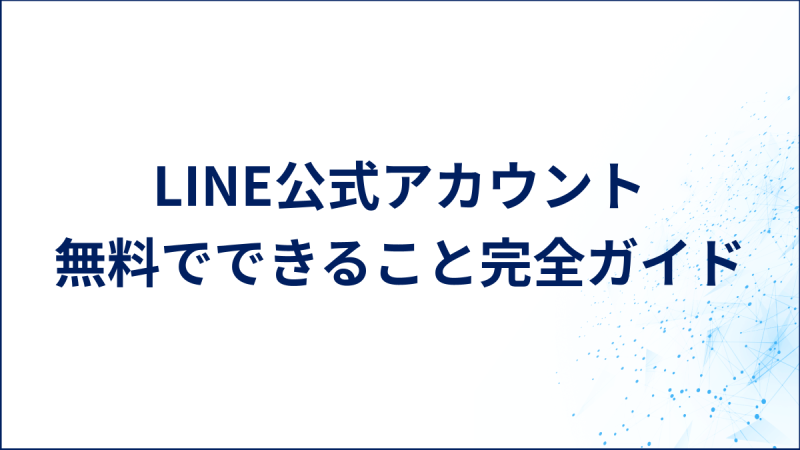
-

-