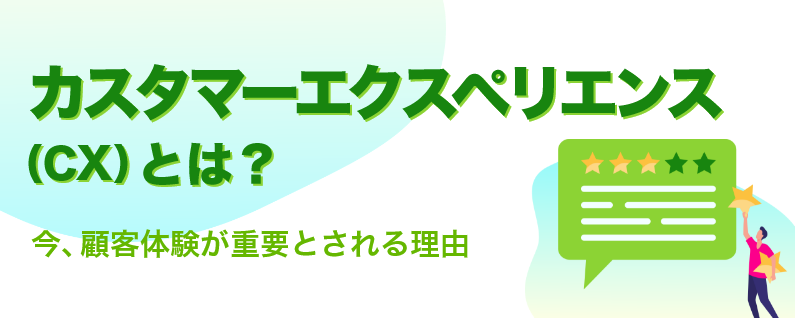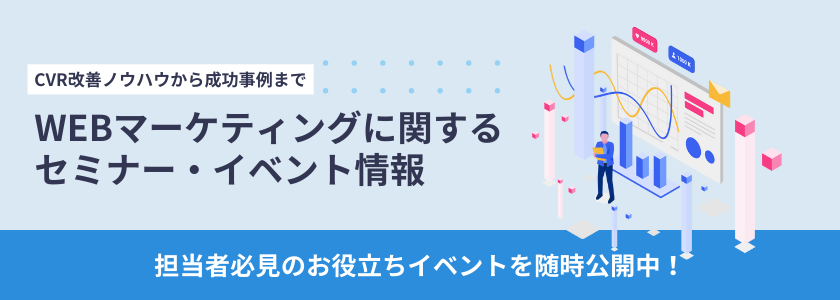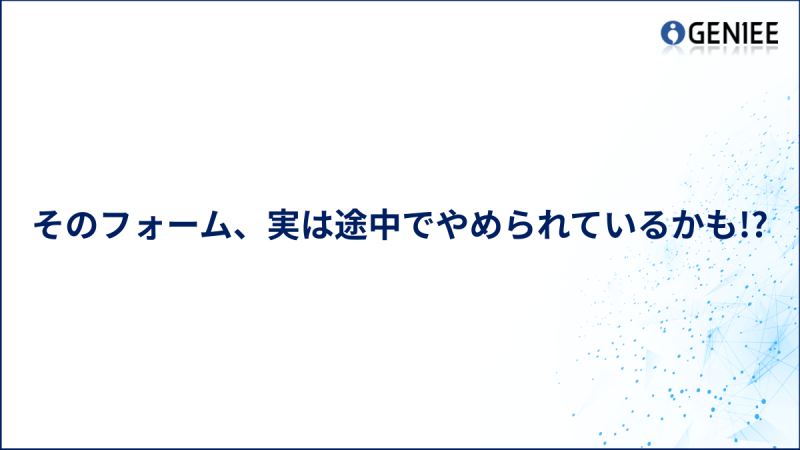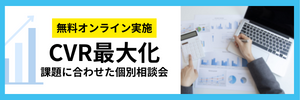ネット広告やSNSでの発信が当たり前となった今、商品やサービスの「魅力」だけでは選ばれにくくなっています。
そんな中、企業が注目しているのが、顧客が商品・サービスを通じて得る体験「カスタマーエクスペリエンス(CX)」です。
例えば、ECサイトで迷わずに商品を選び、スムーズに購入できたとき。あるいは、問い合わせの返信が丁寧で、想像以上の対応をしてもらえたとき。
こうした体験の一つひとつが、「また利用したい」「この会社は信頼できる」といった印象につながっていきます。
本記事では、カスタマーエクスペリエンス(CX)の意味や改善ポイントを解説し、なぜ今CXが重要視されているのかを紐解いていきます。

目次
カスタマーエクスペリエンス(CX)とは
とは-1024x576.png)
カスタマーエクスペリエンス(CX)とは、Customer Experienceの略で、日本語では「顧客体験」や「顧客体験価値」とも訳されます。
この言葉が示すのは、単なる購入による満足感だけでなく、顧客が企業と関わるあらゆる場面で感じる体験全体です。
たとえば、Webサイトでの情報収集、問い合わせ時の対応、商品が届くまでの過程、購入後のフォローまでのすべてがCXの一部といえます。
SNSや口コミの影響力が高まる現代では、こうした「体験」の質が企業のブランド価値や顧客ロイヤルティに直結します。
一度の購入だけでなく、「また選びたい」「誰かに勧めたい」と思わせるようなポジティブな体験こそが、長期的な売上やファンの獲得に結びつくのです。
UXとの違い
カスタマーエクスペリエンス(CX)とよく似た言葉に、ユーザーエクスペリエンス(UX)があります。
どちらも「体験価値」に関わる概念ですが、それぞれの範囲や目的には明確な違いがあります。
UXは、Webサイトやアプリ、製品などを利用する際の使いやすさや快適さに焦点を当てた体験です。たとえば、ECサイトで迷わず商品を探せる、操作が直感的でストレスがない、といった体験がUXにあたります。
一方CXは、UXを含むもっと広い概念で、商品・サービスに出会ってから購入・利用・その後のサポートに至るまでのすべての顧客接点で得られる体験を対象としています。
そのため、UXがCXを構成する一要素ともいえます。
なぜ今、カスタマーエクスペリエンスが重要なのか
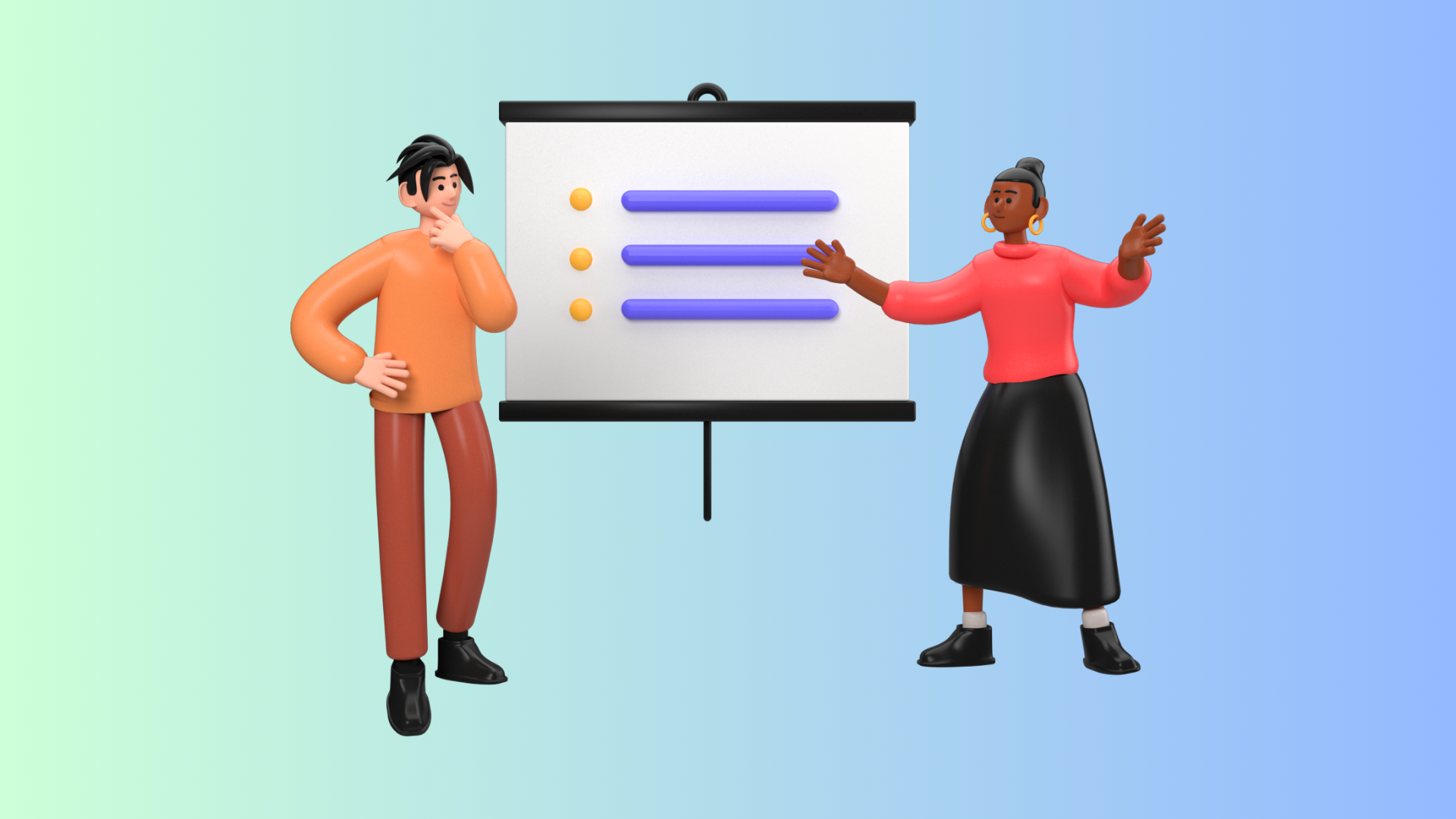
今、多くの市場で似たような製品やサービスがあふれ、価格やスペックだけでの差別化が難しくなっています。
消費者は、店舗で商品を確認し、ネットで最安値を探したり、Webサイトで複数の製品を比較し、自分に合ったものを選びます。このような購買行動が当たり前になり、企業の提供価値が「モノ」だけでは判断されにくい時代になっています。
さらに、ある調査によると、ユーザーの50%は1度でも不満を感じたら競合に乗り換えると言われており、その体験が2回以上になると、その割合は80%にまで上昇するとも報告されています。
つまり、顧客に選ばれ続けるためには、価格や機能以上に「体験の質」が重視されているのです。
こうした背景から、企業が差別化を図る上で注目されているのが「カスタマーエクスペリエンス(CX)」です。
たとえば、店舗の雰囲気、キャンペーンの魅力、購入後のサポート対応など、あらゆる接点で得られる「体験の心地よさ」が、顧客に価値として認識されるようになっています。
実際、マーケティングの権威であるフィリップ・コトラー氏も、著書『マーケティング・マネジメント(2006)』の中で、
「顧客満足度、ロイヤルティ、顧客収益性といった指標が、企業の業績に重大な影響を与える」
と述べています。
つまり、CXは「顧客に選ばれる理由」をつくる経営資源のひとつであり、企業の成長を左右する重要な要素になってきているのです。
カスタマーエクスペリエンス(CX)を構成する主要な要素
を構成する主要な要素-1024x576.png)
カスタマーエクスペリエンス(CX)は、単なる「接客の良し悪し」や「使いやすさ」だけでは成り立ちません。
企業と顧客が出会ってから関係を築き、長期的な信頼へと発展していくためには、いくつもの要素が関わっています。
ここでは、CXを構成する4つの重要な要素をご紹介します。
エンゲージメント(顧客との関係構築)
エンゲージメントとは、顧客と企業の間に築かれる信頼やつながりのことです。
メールやSNSでのコミュニケーション、イベント参加、購入後のフォローアップなどを通じて、一方的ではない「対話」や「共感」が生まれると、顧客のロイヤルティは自然と高まっていきます。
パーソナライズ(個別最適化)
顧客の属性や行動データに基づいて、一人ひとりに最適な情報や体験を提供することがCX向上には欠かせません。
たとえば、ECサイトでのレコメンド、リターゲティング広告、過去の購入履歴に基づいたメール配信などがパーソナライズ施策にあたります。
顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じると、満足度や再購買意欲が高まります。
オムニチャネル(統合された接点設計)
現代の顧客は、Webサイト、SNS、LINE、実店舗、コールセンターなど、複数のチャネルを横断しながら商品やサービスに触れています。
そのため、どのチャネルでも一貫性のある情報・対応・体験を提供するオムニチャネル設計が求められます。
たとえば、Webで下調べした内容を実店舗でもスムーズに引き継げるようにしたり、LINEでの問い合わせ履歴をECサイトでも参照できるような工夫が、CXを大きく左右します。
カスタマーサポート(問題解決力)
商品やサービスに不満を持った瞬間、対応の速さや丁寧さがCXの印象を大きく左右します。
電話・メール・チャットボットなど多様なチャネルで迅速かつ的確にサポートできる体制があると、顧客は安心して継続的な関係を築くことができます。
また、FAQの充実や自己解決できる導線設計もCX改善の鍵となります。
カスタマーエクスペリエンスの改善で得られるメリット
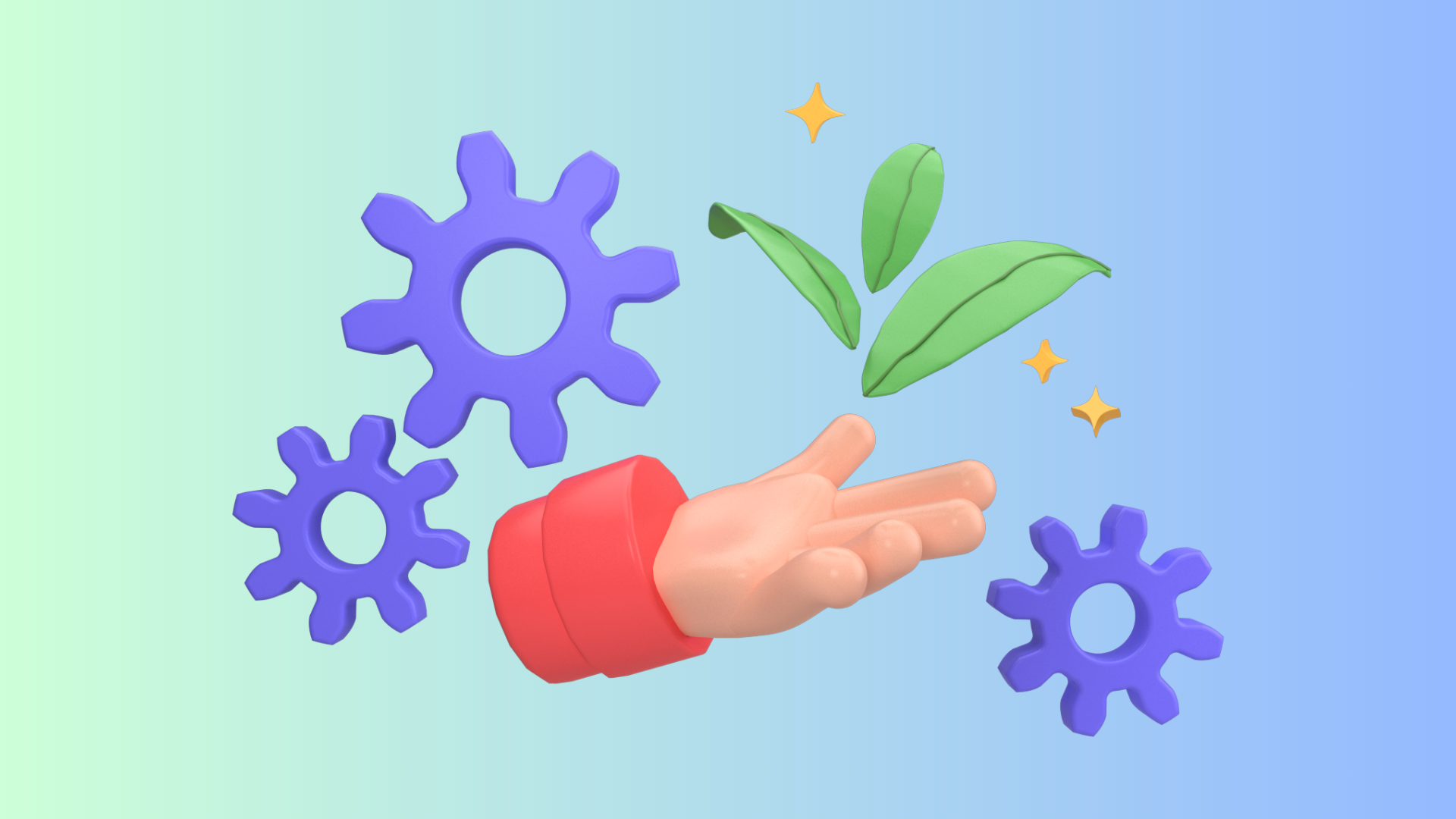
カスタマーエクスペリエンス(CX)を高めることは、もはや選ばれる企業になるための「前提条件」ともいえます。
競合他社との差別化が難しくなった今、CXの質が顧客との関係性や売上に大きく影響を与えます。
ここでは、CX改善によって得られる6つの主なメリットを、マーケティング視点から解説します。
顧客満足度が向上する
製品やサービスを購入する際、店内に心地よい音楽が流れていて雰囲気が良かったり、店員が親切かつわかりやすい説明をしてくれたりと、ユーザーの期待以上のカスタマーエクスペリエンスが提供できた場合、顧客満足度が向上します。
近年では、リアル店舗だけでなくオンラインでも一貫性のある対応が求められており、デジタルとリアルの両面で顧客とのコミュニケーションを設計することが不可欠です。
さらに、商品やサービスに加え、イベントなどの「体験型コンテンツ」もCX向上に寄与します。
エンゲージメントが高まり、リピーターを獲得できる
CXが高い企業は、ユーザーに「また利用したい」「他の人にも勧めたい」という感情を自然に生み出します。
こうしたポジティブな感情は再購入・再来店につながり、リピーターを増やします。
結果として、顧客一人あたりの売上を示すLTV(顧客生涯価値)の最大化にも貢献します。
競合他社との差別化を図ることができる
製品や価格では違いが出しにくい市場において、CXは数少ない差別化ポイントです。
たとえば、スターバックスは「コーヒーを提供する場」ではなく、「心地よく過ごせる“サードプレイス”」を提供することで、他社と一線を画しました。
無料Wi-Fiやパーソナライズされた注文、ホスピタリティあふれる接客など、「ここでしか体験できない価値」がブランドの独自性をつくっています。
ブランドイメージが向上する
CXは、企業のブランドイメージを形づくる「体験の積み重ね」です。
購入前・利用中・購入後といった各フェーズにおいて、ユーザーの期待を超える体験を提供できれば、信頼や愛着が生まれ、ブランドに対する印象は自然と向上します。
このような一貫した好印象の積み重ねが、ファンを生み出す土台となります。
ユーザーの口コミによる宣伝効果が期待できる
エンゲージメントの高いユーザーは、SNSでの投稿やレビューによって自発的に企業の魅力を広めてくれます。
こうしたポジティブな情報は、企業が発信する広告よりも信頼性が高く、購買意欲を強く刺激します。
さらに、ユーザーによる自然な拡散は、広告費削減にもつながります。
売上の安定化に繋がる
CXを重視した取り組みによって顧客の満足度やロイヤルティが高まると、リピーターが増え、乗り換えリスクが減少します。
また、口コミや紹介によって新規顧客も獲得しやすくなり、集客コストを抑えながら安定した売上が見込めるようになります。

カスタマーエクスペリエンス(CX)を改善するための4ステップ
を改善するための4ステップ-1024x576.png)
CXは一朝一夕で成果が出るものではなく、計画的かつ継続的な取り組みが必要です。
ここでは、CXを改善・強化していくための基本的な4つのステップをご紹介します。
ステップ1:VoC(顧客の声)の収集とNPSの活用
CX改善の第一歩は、顧客の本音を正しく把握することです。アンケートやインタビュー、カスタマーサポートへの問い合わせ内容、SNSの投稿など、あらゆるチャネルから顧客の声(VoC:Voice of Customer)を集めましょう。
特に活用されている指標がNPS(ネット・プロモーター・スコア)です。
「この商品/サービスを友人に勧めたいと思うか?」というシンプルな質問を通じて、顧客のロイヤルティを数値化することができます。
VoCとNPSの分析を通じて、現状のCXの課題がどこにあるのかを明確にしていきましょう。
ステップ2:データ基盤の整備(CRM / CDP / AI)
顧客理解を深めるためには、データを一元管理できる基盤が欠かせません。
CRM(顧客関係管理システム)やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を活用することで、属性・購買履歴・行動データなどを統合し、セグメントごとの最適な対応が可能になります。
オムニチャネルの設計とUI/UXの最適化
顧客は、Web、SNS、アプリ、店舗、LINEなど、複数のチャネルを行き来しています。
そこで重要なのが、どのチャネルでも一貫した体験を提供するオムニチャネル戦略です。
また、各チャネルでの体験を快適にするために、UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)の設計も見直す必要があります。使いやすさや導線の明快さは、CXに大きく影響します。
改善施策の実行とPDCAサイクル
課題が見え、データ基盤とチャネル設計が整ったら、いよいよ改善施策の実行フェーズです。
例えば、「チャットボットを導入して問い合わせ対応を改善」「顧客ごとのレコメンド精度を上げる」といった具体的施策を展開していきます。
重要なのは、一度実施したら終わりにせず、継続的にPDCA(Plan-Do-Check-Act)を回すことです。定期的に効果測定を行い、CXの質を磨き続けることで、顧客との信頼関係をより深めていくことができます。
KPIと成果の測定方法

CX施策を実行したあとは、その効果をしっかりと測定し、次の改善につなげることが重要です。
特に、「どの体験が顧客満足やロイヤルティにつながったのか?」を可視化・定量化することで、継続的な改善の精度が上がります。
ここでは、カスタマーエクスペリエンス向上において代表的なKPI(重要業績評価指標)と、その活用方法をご紹介します。
NPS(ネット・プロモーター・スコア)
顧客ロイヤルティを測る代表的な指標です。
「この商品/サービスを友人や同僚におすすめしますか?」という質問に対する回答をもとに、顧客を「推奨者」「中立者」「批判者」に分類し、スコア化します。
スコアの変化を追うことで、CX改善がどれだけ顧客の信頼や支持につながっているかを評価できます。
顧客満足度(CSAT)
サービスや購入体験の直後に「満足しましたか?」と尋ねる調査で、体験直後の感情を数値化できるシンプルかつ重要な指標です。
特にカスタマーサポートやフォーム送信完了時などに活用でき、改善ポイントの把握に役立ちます。
顧客離反率(チャーンレート)
一定期間内にサービスを解約・利用停止したユーザーの割合です。SaaSやサブスクリプションモデルでは、特に重視されるKPIです。
CXの質が悪い場合、早期離脱につながるため、チャーンの推移を見ることでCXの健全性を確認できます。
フォーム完了率(EFO関連KPI)
資料請求や申し込みなどのフォームにおいて、「どれだけのユーザーが完了まで到達したか」を示す指標です。
ここで注目すべきは、入力体験の質です。たとえば、「入力が面倒」「何を選べばいいかわからない」といった理由での離脱は、CX低下に直結します。
顧客生涯価値(LTV)
1人の顧客が生涯で企業にもたらす利益の合計です。CX向上によってリピーター化や単価UPが進めば、LTVの増加につながります。
カスタマーエクスペリエンスの成功事例

では、どのようにすれば良質なカスタマーエクスペリエンスを実現できるのでしょうか?
ここでは、実際にCX向上に成功している2社の事例を紹介します。
スターバックス|デジタル活用とロイヤリティ設計でCXを強化
スターバックスは、顧客の声に耳を傾け、CXの継続的な改善に取り組んでいる代表的な企業です。
その一例が「Mobile Order & Pay」機能の導入です。
「レジに並ばずに注文したい」「自分好みにカスタマイズしたい」というユーザーの要望を受け、アプリやWebサイトから事前にオーダーと決済ができる仕組みを整備しました。
これにより、待ち時間のストレス軽減とパーソナライズされた注文体験を両立させ、CXを大きく向上させました。
さらに、アプリでは「STARBUCKS REWARDS」というロイヤリティプログラムを提供しています。
54円ごとに「Star」が1つ貯まり、一定数でドリンクやフードと交換可能な仕組みとなっており、アプリの継続利用を促進すると同時に、エンゲージメント強化にもつながっています。
ユニクロ|オンラインとAI活用で不安を解消するCX設計
ユニクロもまた、顧客ニーズに寄り添った体験設計でCXを向上させています。
たとえば、LINE上で使えるAIチャットボット「UNIQLO IQ」では、ユーザーの質問に答えながら、コーディネート提案や在庫状況の確認など、実店舗の店員のような接客体験を提供しています。
「会話しながら選べる」というUXが、顧客満足と利便性の向上に貢献しています。
また、「MYSIZE ASSIST」というサイズ提案サービスも注目です。
身長と体重を入力するだけで、似た体型の人が選んだサイズを提案してくれる仕組みになっており、オンライン購入時の「サイズが合わないかも…」という不安を軽減しています。
さらに、スーツやシャツのセミオーダーサービスでは、Webサイトに自分の採寸データを入力するだけで注文が完了。店舗での採寸も可能なため、オンラインとオフラインをシームレスにつなぐ体験設計が実現されています。
スターバックスもユニクロも、共通しているのは「ユーザーの声をもとに、課題解決につながる体験を設計している」という点です。
ただ機能を追加するのではなく、顧客の行動や心理を的確に捉えたCX設計が、リピート率やブランドロイヤリティを高める結果につながっています。
まとめ|CX向上は「選ばれる企業」になるためのカギ

優れたカスタマーエクスペリエンス(CX)を提供するためには、常に顧客視点で考え、行動することが何より重要です。
ユーザーがどのような期待や課題を持っているのかを深く理解し、その体験全体に価値を提供することで、単なる価格やスペックではない「共感」や「信頼」による選ばれる理由を築くことができます。
製品やサービスの品質だけで勝負する時代は終わりました。
これからは、CXという体験価値を高めることで、競合と差別化し、長期的なファンの獲得と売上の安定化を実現する企業が選ばれていきます。
カスタマーエクスペリエンス向上の第一歩|GENIEE CHAT
ユーザーにとって「最初の接点」であるWebフォームの体験も、カスタマーエクスペリエンスの一部です。せっかくサイトに訪問してくれても、入力が面倒だったり、途中で離脱してしまえば機会損失になってしまいます。
そんな課題を解決するのが、チャットボット型の入力フォーム「GENIEE CHAT」です。
会話形式でスムーズに入力を促し、離脱率を大幅に改善することが可能です。
チャット型EFOツール「GENIEE CHAT」
株式会社ジーニーでは、入力フォームを改善し、コンバージョン率を向上させるための「GENIEE CHAT」を提供しています。
Webサイト上に設置している入力フォームをチャット型に置き換えることで、スムーズなフォーム入力が可能になり、その結果、フォーム離脱率を低減し、入力完了率の向上が期待できます。

詳しくはこちらから資料ダウンロード
関連記事
-
マーケティング完全ガイド-800x450.png)
-

-

-

-

-

-

-