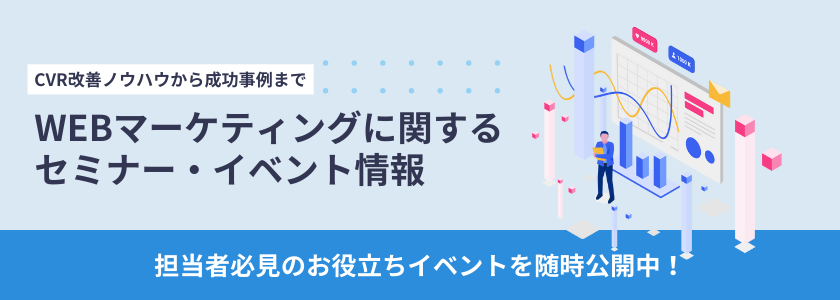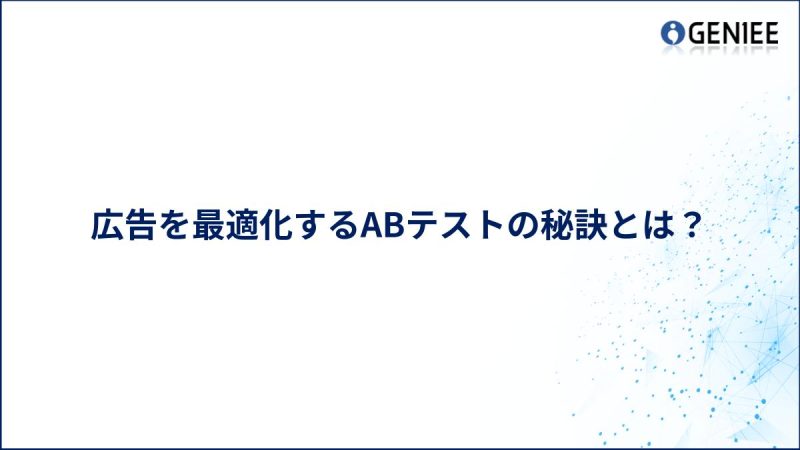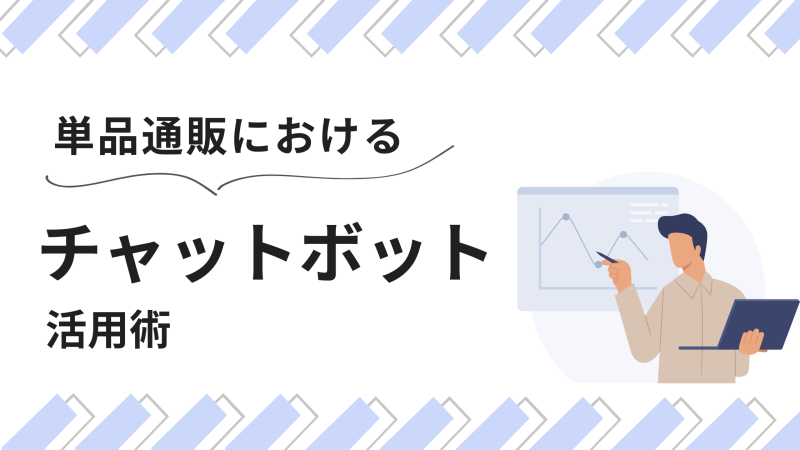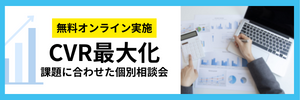ステルスマーケティング(ステマ)は、消費者に対して特定の商品やサービスを宣伝する際に、広告であることを意図的に隠したり、宣伝活動であることを偽ったりするマーケティング手法です。
この手法は、消費者が自然な口コミや推薦として受け取るように仕向けることで、商品やサービスの販売促進を目指します。

目次
ステルスマーケティングの効果・特性

ステマは、特にEC業界やD2C業者において多く活用され、その中でも、化粧品、サプリメント、健康食品、デジタルガジェットなどの「コンプレックス商材」のプロモーションとの相性が良い傾向があります。これらの商材は、人に相談しにくい内容であるため、多くの消費者がネットの口コミに頼ることが多いことが要因として考えられます。
また、ステマの効果として以下の2つが挙げられます。
1つ目は、コストを抑えて宣伝できる点です。一般的な広告費用では数十万円から数百万円ほどかかります。しかし、ステマでは一般的な広告出稿と比較して費用がかかりません。
また、良い評価の口コミが多いことから注目を集め、長期的な宣伝効果を得られる可能性があります。
2つ目は、ユーザーの信頼を得られる点です。第三者が投稿することで、ユーザーが信頼を抱いたり、好意的な評価をしたりするなどの心理的効果を得られる可能性があります。
一般的な広告では、ネガティブな印象を抱かれたり、そもそも興味を持ってもらえなかったりする中で、インフルエンサーからの投稿であれば商品に対してポジティブなイメージを抱きやすく、結果として信頼獲得につながります。

ステルスマーケティングの手法
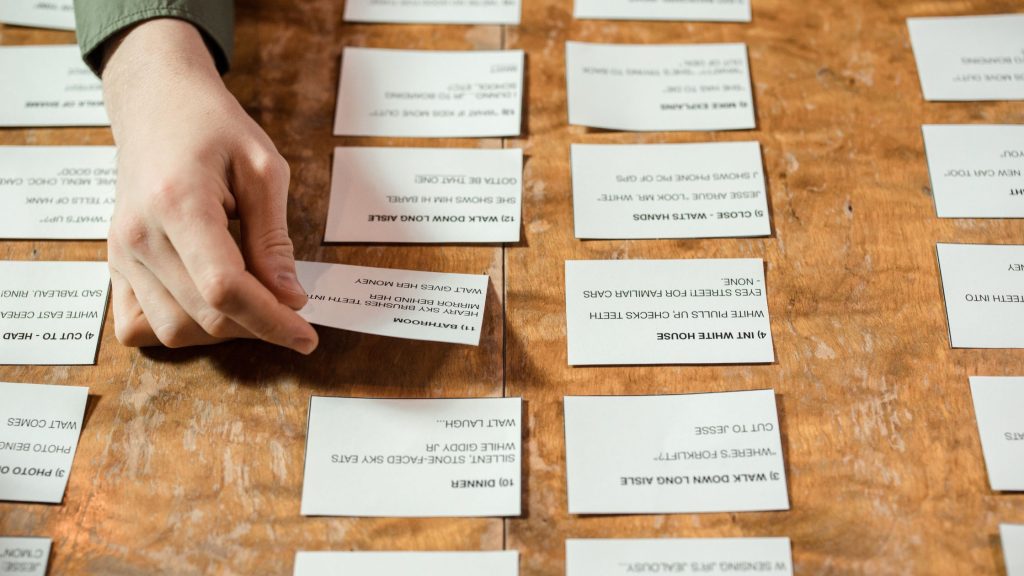
ステマには主に「なりすまし型」と「利益提供型」の2つの手法があります。
なりすまし型
なりすまし型では、従業員や外部の業者が一般消費者になりすまして、SNSやレビューサイトに自社製品の肯定的なレビューや口コミを投稿します。この手法は、「サクラ」や「やらせ」とも呼ばれています。
利益提供型
利益提供型は、芸能人やインフルエンサーに報酬や特典を渡しながら、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝をする手法です。
SNSの普及に伴い、この手法が急速に広まりました。そのため、企業は広告宣伝費を抑えつつ、口コミ効果を狙えるため非常に効果的です。
しかし、消費者には宣伝であることが明示されないため、問題視されています。
ステルスマーケティングの事例

ここでは、実際に起きたステルスマーケティングの事例について紹介します。
なりすまし型の例として、食べログと化粧品会社での事例が挙げられます。
食べログでの事例
これは食べログ内で、ステマが行われていた例になります。
食べログでは、利用者が書き込んだ口コミや点数を元にランキングが掲載されることが特徴です。しかし、飲食店に好意的な評価を投稿し、ランキングを上げる見返りに金銭を受け取る業者が39社いたことが明るみになりました。
化粧品会社での事例
これは化粧品会社の広報担当がSNS上で美容系インフルエンサーになりすました例になります。SNS上で、自身が勤務する会社やそのグループ会社の商品を高く評価する内容の投稿を複数回行い、問題となりました。
一方、利益提供型では、芸能人やインフルエンサーが企業から報酬を受け取り、広告であることを隠してSNSなどで商品を宣伝します。
利益提供型の例として、ペニーオークションや吉本興業の事例が挙げられます。
ペニーオークションの事例
これは複数の芸能人がペニーオークションで購入したことを投稿した例になります。
複数の芸能人がペニーオークションで購入したことを投稿したことで、やらせの疑惑が浮上しました。その後、投稿した芸能人が報酬を受け取り、落札せずに投稿していたことやペニーオークションが詐欺のような仕組みで運営されていることが発覚しました。
その結果、ペニーオークションの経営者は逮捕され、投稿した芸能人はバッシングを受けました。
吉本興業の事例
これは吉本興業に所属しているお笑い芸人のミキが、報酬を受け取っているにも関わらず、投稿に宣伝であることを表示せず、観光地を紹介した例です。
京都市は京都にゆかりのある芸能人としてミキに依頼し、PR表記なしの投稿で100件程度のRT数を獲得したことで多くの批判が寄せられました。
ステルスマーケティングの問題点とリスク
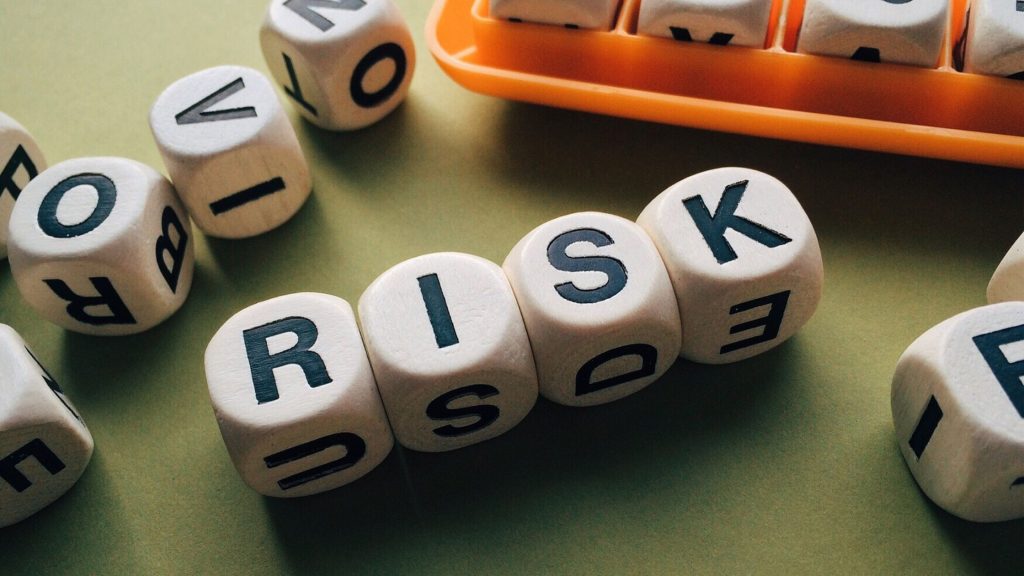
ステルスマーケティングの問題点
ステマは、「広告」であることを消費者が認識しにくいという側面を抱えています。
一般広告には、ある程度の誇張や誇大表現が含まれることがありますが、消費者はそれを「広告・宣伝」として受け止めるため、情報を適切に判断することができます。
しかし、ステマはなりすましやインフルエンサーからの発信といった形で、その広告性が隠されているため、商品やサービスに関して実際とは異なる印象を持たせることがあります。
これは、消費者を誤認させる不適切な表示となり、2023年10月1日からは景品表示法により不当表示として規制されるようになりました。
ステルスマーケティングのリスク
ステマを行うと、企業の信頼性や大きく損なわれるリスクがあります。これは、消費者がステマが発覚時に「だまされた」と感じ、不信感を抱くためです。その結果、商品やサービスだけでなく、企業全体の信用も失われてしまいます。
また、ステマの発覚は当該企業に留まらず、競合他社や広告業界全体の信頼にも悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、一度ネガティブなイメージがつくと、失った信用を回復するのは非常に困難です。このように、企業にとっては長期的なダメージとなるでしょう。
ステルスマーケティングに対する法規制

前述の通り、2023年10月1日より、ステマは景品表示法上の不当表示として規制されるようになりました。この改正は、広告であることを隠して行われる宣伝活動を禁止し、消費者を誤解させるような不当な表示を取り締まることを目的としています。
今回、規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。一方で、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
したがって、企業はより透明性の高いマーケティング活動を行うことが求められるようになりました。
詳細:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
ステルスマーケティングへの対策

ステマは消費者の信頼を損ない、企業の評判に悪影響を及ぼす可能性があります。そこで、ステマへの対策として、3つのアプローチを紹介します。
1. 広告であることを明示する
消費者がコンテンツを見た瞬間に、それが広告であることを理解できるようにすることが重要です。隠微な表示ではなく、明確かつはっきりとした方法で広告であることを示す必要があります。SNSでの宣伝にはハッシュタグを活用することが効果的です。
また、金銭のやり取りが発生している場合は特に表記に注意が必要です。
- 商品を受け取っている場合: #モニター、#サービス提供、#プレゼント企画
- 金銭を受け取っている場合: #PR、#タイアップ
2. 広告主を明確にする
広告であることを示すだけでなく、その広告が誰からの依頼であるかを明確にすることも重要です。広告主とインフルエンサー(投稿者)との関係性が消費者に分かるような表現を用いることで、透明性を高めることができます。
3. 正しい情報を発信する
消費者の注意を引くために誇張された表現や虚偽の情報を使用することは避けるべきです。また、レビューの改ざんやインフルエンサーへの投稿内容の強要も、信頼を損なう行為です。
インフルエンサーが「いいね」やフォロワー数、視聴回数を不正に増やす行為も問題視されています。ステマを実施するにあたり、企業とインフルエンサー双方が誠実さを持って行動することが求められます。
まとめ
ステマは一時的な販売促進効果をもたらすかもしれませんが、消費者の信頼を損ない、企業の長期的なイメージに悪影響を及ぼすリスクがあります。法規制の強化により、企業はより倫理的で透明性の高いマーケティング戦略を追求する必要があります。

関連記事
-
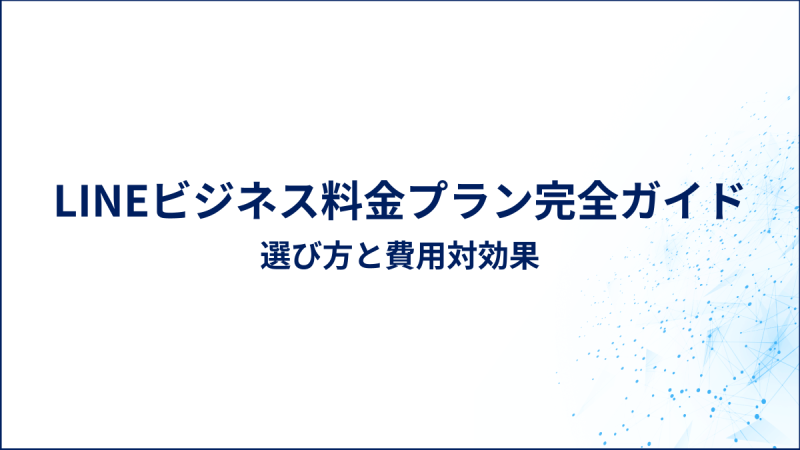
-
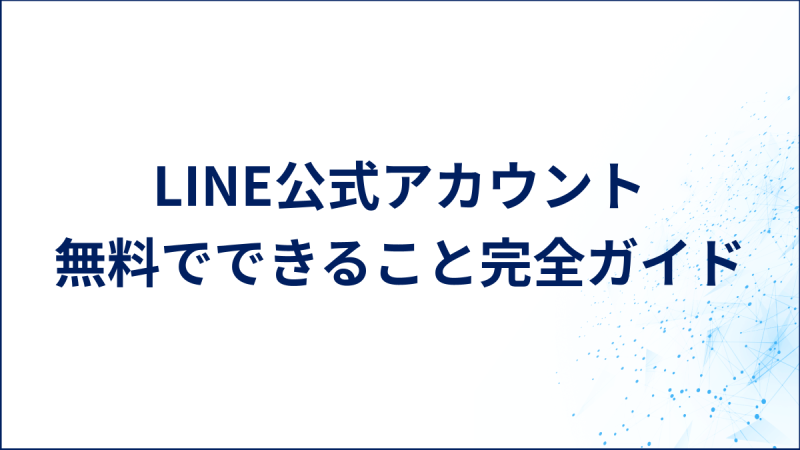
-

-
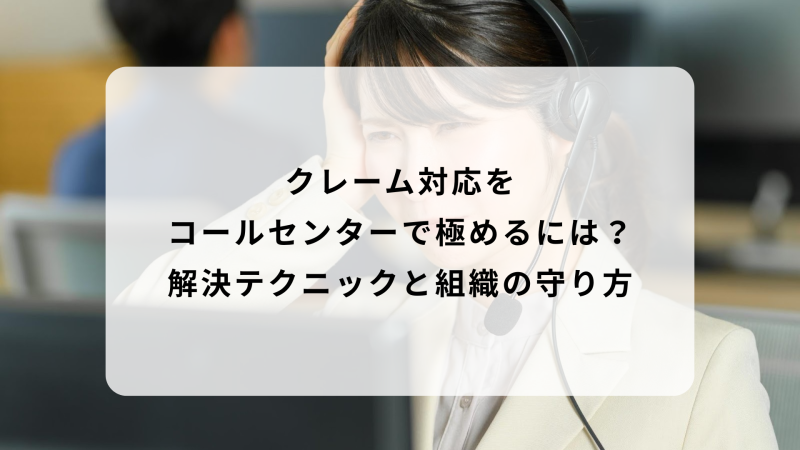
-

-
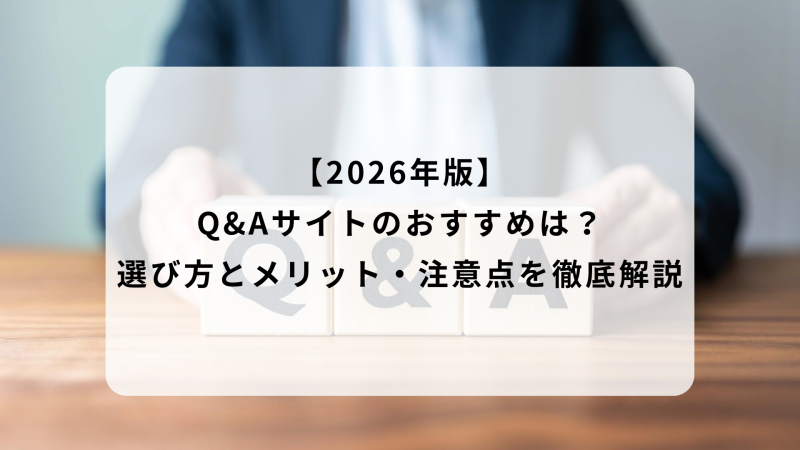
-

-