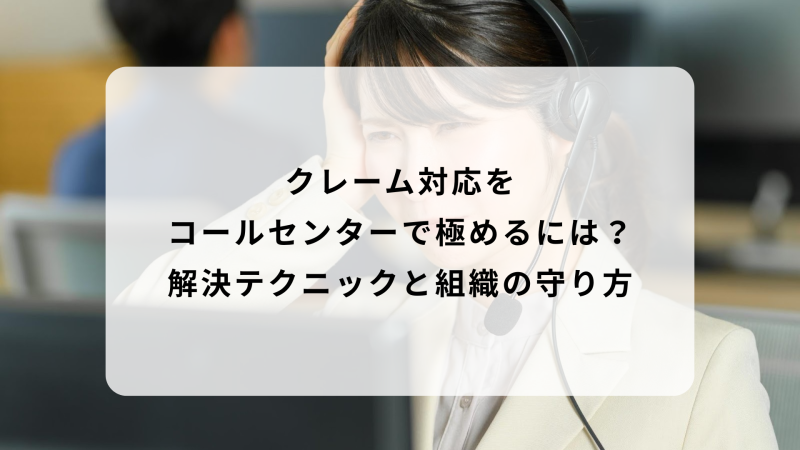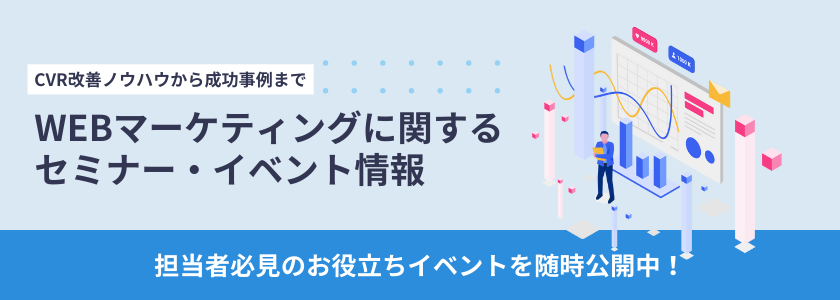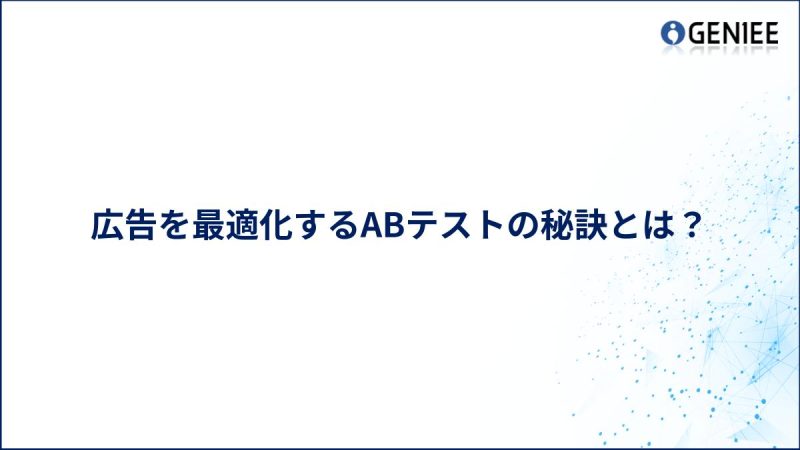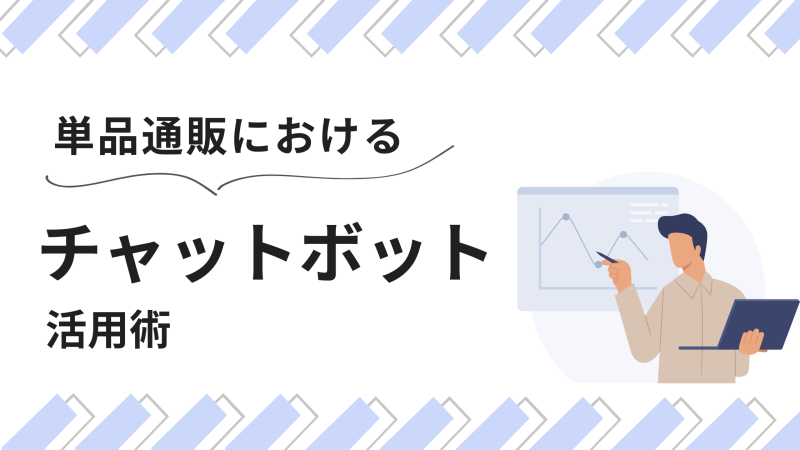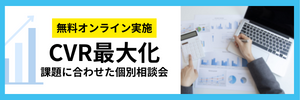カゴ落ちとは、購入手続きを完了せずに離脱してしまう現象のことを指します。これは、ECサイトの売上が伸びない原因の一つであり、対策をきちんと行うことで売上向上を見込むことができます。
「ECサイトに訪れたお客さまが、商品をカートに入れたのに購入しないまま離脱してしまう…。」
「せっかく広告予算を使ったのに、回収ができない…。」
本記事では、カゴ落ちが発生してしまう原因やその対策について解説していきます。

目次
カゴ落ちとは?

カゴ落ちとは、サイトに訪れたユーザーが商品をカートに入れたものの、決済をせずにサイトから離脱してしまい、購入に至らなかった状態を指します。(「カート放棄」とも呼ばれます。)
カゴ落ちは、多くのECサイトに共通する課題です。多ければ多いほど売上機会の損失が生じ、事業の成長を妨げます。
カゴ落ちしたユーザーは、一度商品をカートに入れています。そのため、商品に対して興味や関心を持っており、決して購入意欲がないわけではありません。多くのユーザーがサイトに訪れてすぐに離脱してしまう現状を考えると、カゴ落ちユーザーは購入の可能性が高い層であると言えます。
しかし、後述するようなさまざまな理由によってカゴ落ちは発生してしまうのです。
カゴ落ちの割合と売上への影響
カゴ落ちが売上にどのような影響を与えているのか気になる方も多いでしょう。
アメリカの調査機関Baymard Instituteによると、世界のECサイトにおけるカゴ落ち率の平均は約70%にのぼります。つまり、10人のうち7人が商品をカートに入れても購入に至っていないということです。(参考:Baymard Institute「Cart Abandonment Rate」)
また、日本のイー・エージェンシーが実施した調査では、カゴ落ちによる機会損失額が、平均して売上の約2.5倍に達していることが明らかになりました。これは、カゴ落ちが売上機会の大幅な損失につながっていることを示しています。(参考:イー・エージェンシー「ネットショップの機会損失調査」)
このように、カゴ落ちは売上に大きな影響を与えていることがわかります。そのため、その原因を正しく把握し、効果的な対策を講じることが非常に重要です。
カゴ落ちの理由と対策

カゴ落ちはどのような理由によって発生するのか。ここでは、主に考えられる5つの理由をみていきましょう。
1.会員登録が手間
多くのECサイトでは購入手続きの際に会員登録を求められます。入力項目が多すぎたり、生年月日などの購入に不要と思われる情報を求められたりすると、ユーザーは手間を感じて離脱してしまいます。特に、初めて利用するサイトでは、個人情報の提供に慎重になる傾向が強いです。そのため、登録のハードルが高いと感じると離脱率が上がります。
また、パスワード設定やメール認証などの手続きが複雑だと、途中離脱の原因となります。
対策:会員登録の簡易化とゲスト購入の導入の手配
会員登録の入力項目を必要最低限に絞り、できるだけ簡単に登録できるようにしましょう。例えば、住所や電話番号の入力を購入後に任意で求める方法があります。SNSアカウント連携によるワンクリック登録も効果的です。また、会員登録なしで購入できる「ゲスト購入」も効果が高いです。ゲスト購入は特に初回利用者の購入率を高める施策として有効です。
2.送料や手数料が高い
送料や手数料、消費税などの追加費用が決済画面で初めて明らかになる場合があります。
ユーザーは商品ページの金額を見て購入を決めていることが多いです。そのため、決済画面で合計金額を見て「こんなに送料や手数料がかかるのか・・。」と、そのまま離脱してしまうことも少なくありません。
対策:合計金額の明示と送料無料の工夫
送料や手数料がかかる場合は、商品ページの時点で明記しましょう。送料を含めた総額を表示することで、透明性を高め、ユーザーの不安を軽減できます。さらに、送料無料キャンペーンや「〇〇円以上購入で送料無料!」といった条件を設けることで、ユーザーの購入意欲を高めることが可能です。
3.決済手段の制限
ユーザーの年齢やライフスタイル、地域によって利用したい決済方法は多様です。若年層はスマホ決済や後払い決済を好む傾向があります。一方で、高齢者は代引きや銀行振込を選ぶこともあります。また、クレジットカードを持っていなかったり、使いたくない人も一定数存在します。決済手段が限定されていると、購入を断念するケースが増え、カゴ落ちにつながります。
対策:多様な決済手段の提供
多様な決済方法を用意し、幅広いユーザーのニーズに対応しましょう。特にスマホ決済の導入は若年層の取り込みに効果的です。また、決済手段ごとの手数料や利用条件をわかりやすく表示しましょう。ユーザーが安心して選択できる環境を整えることも重要です。
4.エラーの発生
カートに商品を追加したり決済手続きを進める際にエラーが発生すると、ユーザーはストレスを感じてしまいます。その結果、購入意欲が急激に低下します。特にスマホ利用者が増えているため、表示速度や操作性の悪さは離脱の大きな要因です。ページの読み込みが遅い、ボタン無反応などの問題は、ユーザー体験を損ねていまいます。
対策:システムの安定化と高速化
サーバー強化を行い、ページ表示速度を改善しましょう。画像やスクリプトの最適化、CDNの活用、キャッシュの適切な設定なども効果的です。さらに、モバイルファーストの設計を心がけることも重要です。スマホユーザーが快適に操作できる環境を整備することが離脱防止に直結します。
5. サイトへの不信感
運営会社の情報が不明瞭だと、ユーザーは安心して購入できません。また、セキュリティ対策が不十分だと、クレジットカード情報の入力をためらいます。さらに、返品ポリシーが不明確や、条件が厳しすぎる場合も、購入を躊躇させる要因です。信頼性の確保をすることで、売上向上にも直結します。
対策:運営情報・セキュリティ対策の明示と返品ポリシーの明確化
特定商取引法に基づく表記を明確にしましょう。連絡先や所在地、営業時間などの情報をわかりやすく掲載すると良いです。SSLサーバー証明書の表示や常時SSL対応などのセキュリティ対策をサイト上で示すことで、ユーザーの信頼を獲得します。
また、返品条件をわかりやすく提示しましょう。ユーザーにとって公平かつ柔軟な内容にすることで、不安を軽減し購入を促進します。返品無料キャンペーンや返品期限の延長などのサービスも信頼感向上に寄与します。
ユーザーを呼び戻す「カゴ落ちメール」の効果的な活用

カゴ落ちしたユーザーをECサイトに再度呼び戻す方法があります。一般的にはリターゲティング広告やSNS、一斉配信のメールマガジン、ネット広告などが活用されます。これらは広く使われている手法ですが、一方的な情報発信となりやすいです。そのため、効果が限定的であるという課題があります。
そこで近年注目されているのが「カゴ落ちメール」です。カートに商品を入れたまま購入に至っていないユーザーに対して、買い忘れをリマインドするメールです。カゴ落ちメールには以下のような効果が期待されています。
- 購買意欲を再喚起し、再びECサイトに訪問してもらう
- 購入を迷っているユーザーの背中を押す
- 他のECサイトへの流出を防ぐ
カゴ落ちメールが効果的な理由
購入しようと思った矢先に、「急な電話がかかってきた。」「電波の届きにくい場所に移動した。」など、ユーザーはさまざまな理由で途中離脱してしまうことがあります。こうした状況には、迅速かつ丁寧なフォローアップを行うことが重要です。メールを送ることでユーザーの購入意欲を再度喚起するこが可能です。
特に、入力フォームに途中まで入力しているユーザーは、購入意欲が高いです。つまり、具体的に検討を進めている重要な顧客層です。そのため、適切なタイミングでのリマインドやサポートを行うことで、ユーザーの不安や疑問を解消し、購入へとつなげることが期待できます。
カゴ落ちメールを効果的にするポイント
ただし、メールの送信タイミングや頻度を誤ると、逆効果になることもあります。以下のポイントを押さえて運用することが重要です。
1. 配信のタイミング
カゴ落ちユーザーの中には、忙しい時に商品をカートに入れただけの方や、比較検討中、購入意欲がある方などがいます。こうした方に対して早すぎるタイミングや頻繁なメール送信は不快感を与えかねません。
しかも、商品のカテゴリーや価格帯によっても反応は異なります。ため、テストを繰り返しながら最適なタイミングを見極めることが大切です。
2. メールの件名や見た目の工夫
メールの件名は開封率に大きく影響します。ユーザーの購入をサポートする印象を与える件名を工夫しましょう。例えば、
- 「お買い忘れはございませんか?」
- 「カートに入ったままの商品があります」
- 「購入手続きが完了していません」
など、親切で気遣いのある表現が効果的です。
また、メール本文はテキストだけでなく、HTML形式でカゴ落ちした商品画像や価格をビジュアルに訴求することで、再び購買意欲を刺激できます。
3. 配信の回数
カゴ落ちメールの送信は3回までが一般的に妥当とされています。これを超えるとしつこい印象を与え、逆に離脱を招く恐れがあります。送信回数や間隔もテストしながら調整しましょう。
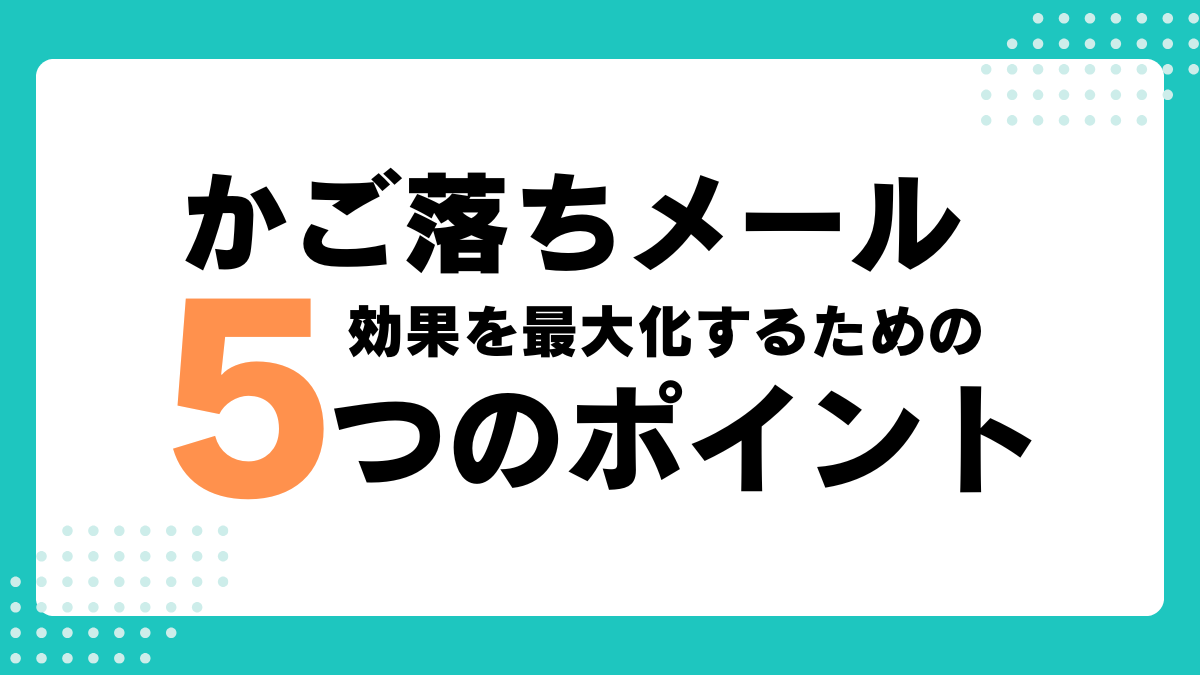
カゴ落ちメール対策ツールの活用

近年では、カゴ落ちメールを自動で送信・管理できるツールもあります。送信タイミングや効果測定、パーソナライズ配信などを支援してもらえるケースもあります。そのため、効率的にカゴ落ち対策を行うことが可能です。カゴ落ちに悩む担当者様は、こうしたツールの導入を検討することをおすすめします。
カゴ落ちツールなら「GENIEE ENGAGE」
株式会社ジーニーではカゴ落ちツール「GENIEE ENGAGE」を提供。WEBサイトの申込フォームに途中まで入力したユーザーに、再アプローチするツールです。メールのみならず、開封率の高いSMSを活用して引き上げ率を最大化します。

メールやSMSの送信回数やタイミングは自由に設定できます。そのため、ユーザーに適切なタイミングでリマインドを送ることが可能です。これにより、メールの開封率が上がり、購入につながりやすくなります。
また、料金は成果報酬型で、コンバージョンがなければ費用は発生しません。さらに、商材に合わせたクリエイティブを無償で制作。
そのため、リスクを抑えて導入が可能です。
「GENIEE ENGAGE」は、ECサイトだけでなく、不動産や人材系の企業様にも導入いただいております。
「GENIEE ENGAGE」資料のお申込みは下記フォームから
関連記事
-

-

-
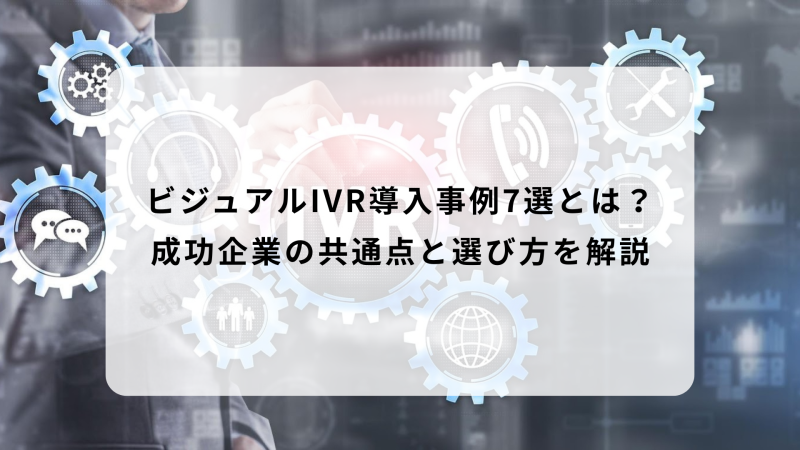
-

-
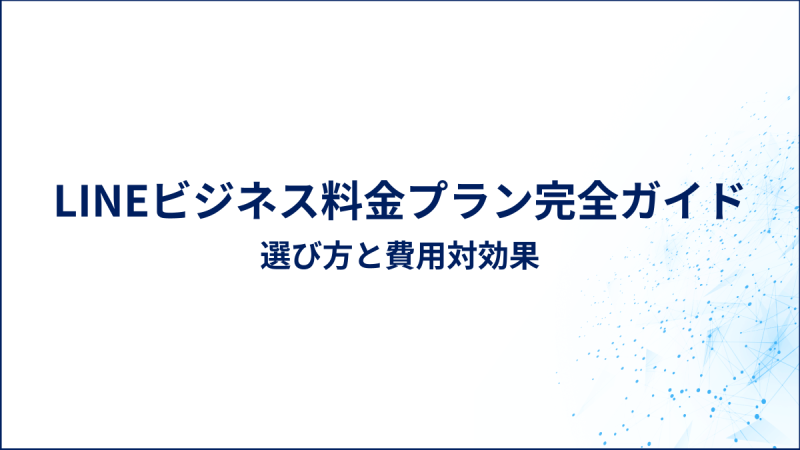
-
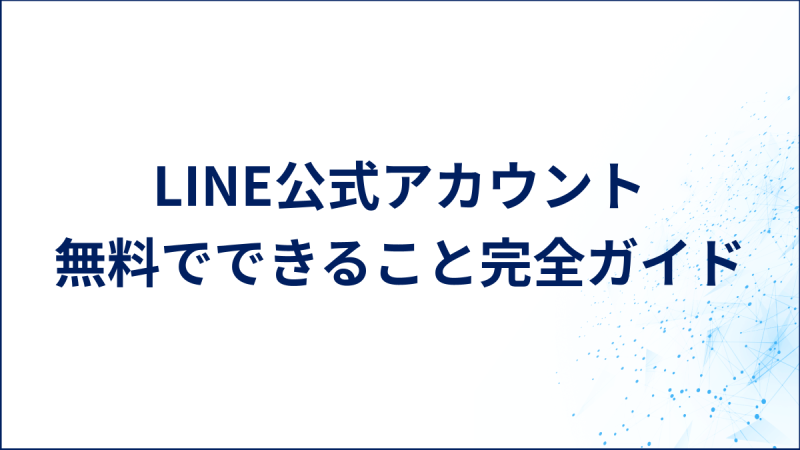
-

-