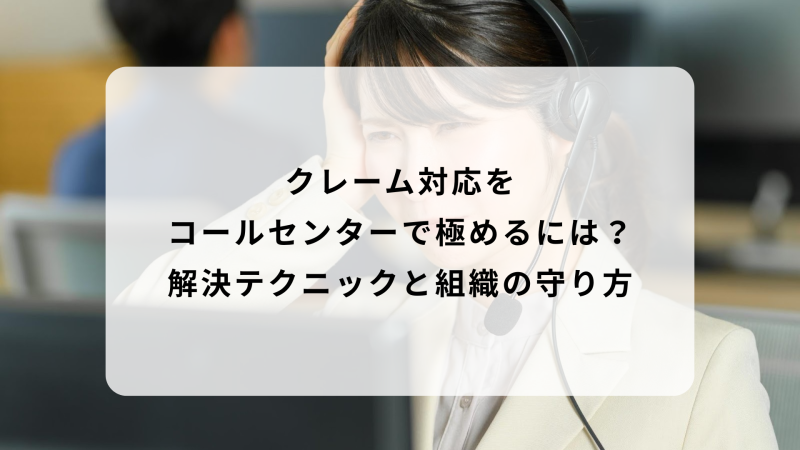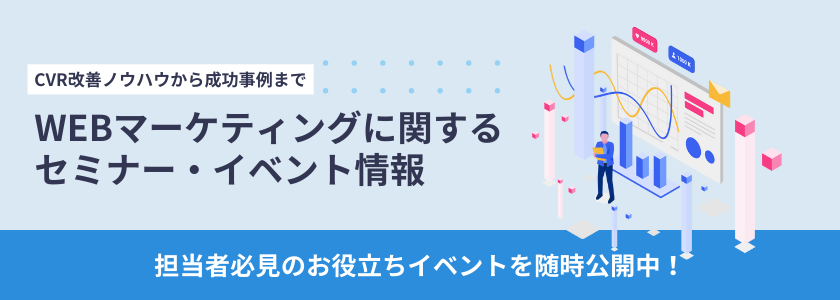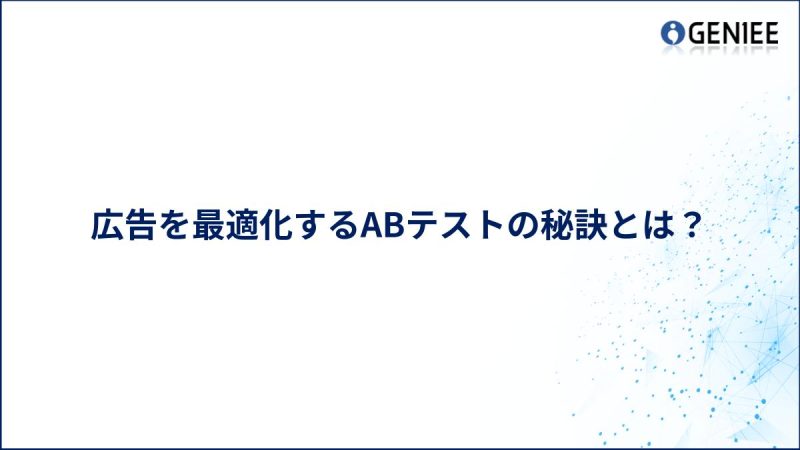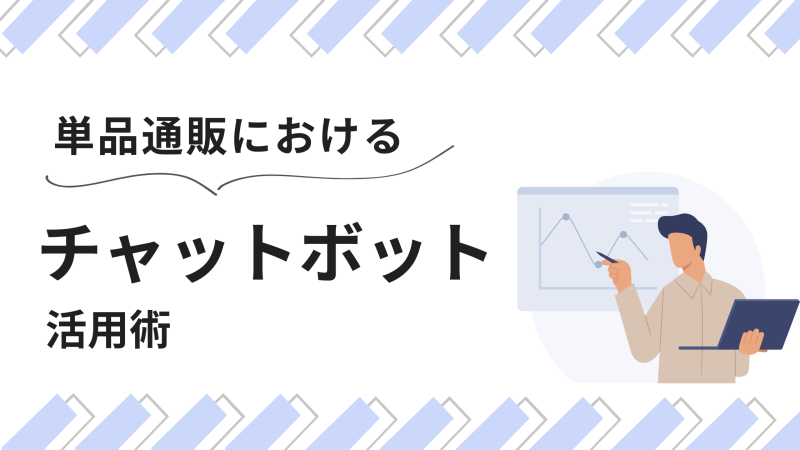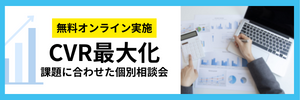Direct to Consumerの略称であるD2C。
従来はB2Bとして問屋や小売店を間に挟み消費者に商品を販売していたメーカーが、独自の販売チャネルで直接消費者に向けて自社商品を販売するビジネスモデルです。特にECサイトを通じた売上は年々増加していて、2025年には3兆円規模に達する見込みです。
なぜ、D2CはEC業界で主流になりつつあるのでしょう。
今回はその理由や成功事例を見つつ、成果を上げるためのポイントをお伝えします。

今現在D2CがEC業界において主流のワケ

2021年7月に経済産業省が公開した、「令和2年度(2020年)電子商取引に関する市場調査(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf)」によると、米国では2020年のECによるD2Cの売上高は178億USドル(推計・前年比24.3%増)です。
今後は日本も同様にD2Cの売上高が向上すると予測されていて、EC業界の主流は従来の小売店舗が消費者に商品を販売するB2CからD2Cへと変化しつつあります。ここではその主流となっている理由を見ていきましょう。
ちなみにD2CでのECサイト運用は、独自店舗での運用と楽天市場やYahoo!ショッピングのようなショッピングモールでの運用のどちらかです。この後に説明するD2Cが主流になりつつある理由は、すべて前者の「独自店舗でのECサイト運用」を前提としています。
高い利益率の実現
D2CがEC業界で主流になりつつある大きな理由が、「収益性の高さ」と「経費削減効果」です。
D2Cは中間マージンや運営手数料、実店舗の敷金・内装・家賃・人件費といった固定費を大幅に削減することができます。その結果、競合よりも価格を抑えた提供が可能になり、収益性を高められるでしょう。
また、固定費や経費が削減されることで、運用にも余裕が生まれ新商品の開発や広告宣伝にコストをかけられるようになります。
それが更なる収益向上につながり、収益拡大の好循環を生みやすくなります。
売り方やマーケティングの自由度が高い
D2Cは、商品開発から接客、販売、アフターフォローまで自社で一貫した管理が可能です。そのため、ブランドメッセージをぶれなく伝えることができ、顧客に愛着を持ってもらえる可能性が高まります。
また、実店舗が地域限定になりがちなのに対し、ECサイトであれば全国を対象にプロモーションや企画が可能です。
例えば、アウトレット販売や優良顧客向けの先行販売・発表会など自社ならではの施策を自由に行うことができます。
顧客と近い距離でさまざまな施策を実施し、自社のブランドや商品に愛着を持った顧客を増やせる機会が増大する点において、D2CのECサイト運用は今後、さらに増加すると考えられます。
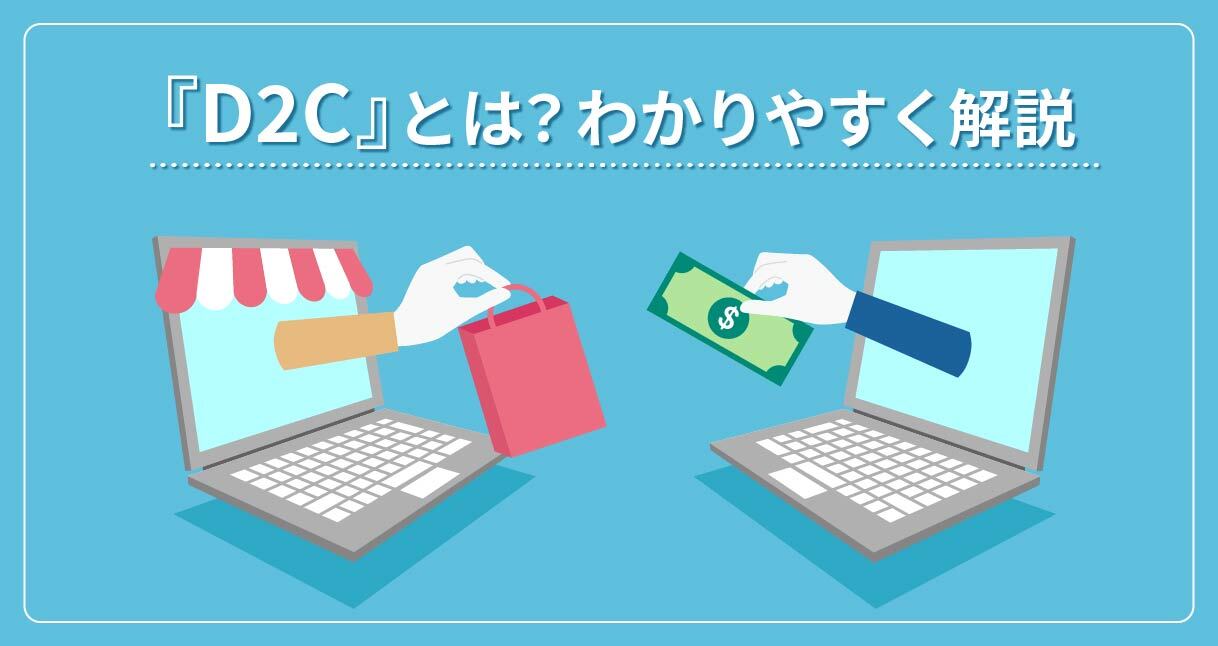
気になる人気D2Cブランド例
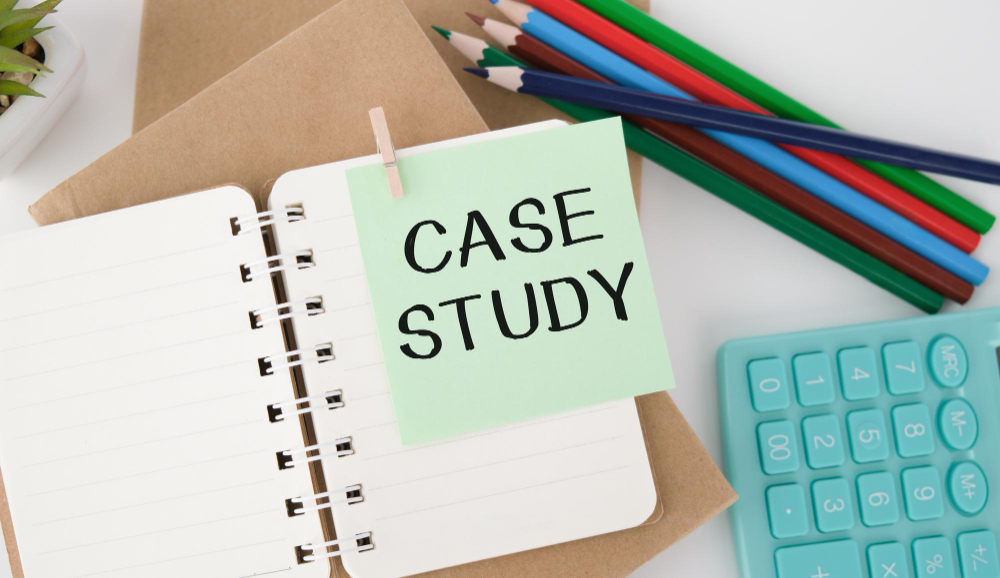
米国ではすでに一つの大きな市場をつくりつつあるD2C。日本でも徐々にその傾向が出始めています。
ここでは、日本と海外でD2Cとしてのブランディングに成功した企業の事例をみていきましょう。
累計販売食数1000万食を突破!:BASE FOOD
東京都目黒区に本社を構えるベースフード株式会社は、26種類のビタミン、ミネラル、たんぱく質、食物繊維など身体に必要な栄養素を含んだ完全栄養食を販売しています。
「忙しくて自炊する時間がない」「免疫力を高めたい」「糖質制限が厳しい」といった課題を抱えている方に向け、2021年10月現在、累計販売食数1,000万食を突破する人気店舗です。
独自店舗では、「完全栄養食とは?」「毎日3食食べる必要があるのか」「理想的な食べ方は?」などに丁寧に回答していて、顧客の不安解消を実現。商品説明でもそれぞれの栄養素について解説しています。
BASE FOODは特殊な食品であることもあり、常に顧客の声を迅速に反映させることが顧客の信頼感獲得につながります。それを実現させるうえでもD2Cは最適な手段の一つであり、それが累計販売食数1,000万食突破につながったのでしょう。
オンライン、オフラインのハイブリッド!:FABRIC TOKYO
東京都渋谷区に本社を構える株式会社FABRIC TOKYO。同社ではデジタル世代のビジネスウェアをカスタムオーダーするサービスを展開しています。
衣料品のECサイトでもっとも難しいのはサイズ感の把握です。特にカスタムオーダーをECサイトだけで完結させるのは簡単ではありません。
そこで同社では、東京を中心に全国15か所で無料採寸・提案を行えるショールーム型店舗を設置。ここで採寸を行い、サイズをクラウドに登録して必要になった際にネット上の独自店舗から注文をする方式を取っています。
自宅近くに店舗がない場合は、自分で採寸を行いそのデータを登録することも可能です。
オフラインで店舗を持つのは、コスト的にはマイナスな面もあるかもしれません。しかし、カスタムオーダーという性質上、オンラインとオフラインをうまく融合させることで顧客体験の向上には大きく貢献しているといえます。
そして、オンラインとオフラインのスムーズな連携はD2Cだからこそ実現したといえるでしょう。
海外の成功例:Warby Parker
ここで一つ海外でのD2C成功事例を紹介します。米国、ニューヨーク州に本社を構えるWarby Parkerは、メガネ・サングラスを販売するメーカーで、世界で初めてD2Cを成功させた企業としても有名です。
2010年に設立した同社では、顧客に対し、気に入ったメガネを最大5つまで無料で5日間試せるサービスを提供しました。
また、どうしても1つに絞れない場合、TwitterやInstagramなどのSNSに「# WarbyHomeTryOn」をつけて投稿すれば担当者からアドバイスがもらえたり、ECサイト上のライブチャットで相談に乗ってもらえたりするサービスも提供。
D2Cならではのサービスに加え、SNSやチャットを活用することで顧客体験価値の向上を実現しています。
老舗ブランドのD2C化:土屋鞄製造所
東京都足立区に本社を構える土屋鞄製造所。1965年創業の老舗で元々はランドセル製造を専門の行う会社としてスタートしました。
その後、2000年に入りEC販売も開始。しかし、開発を外部に依頼していたことで新たなツールの導入や使い勝手の改善に時間がかかり、ECの変化するスピードについていけないといった課題が生まれました。
同社ではこの課題解決に、自社で最小限のWeb開発チームを作成し、開発から運用までのすべてを内製に変更させました。
また、2000年代に入ってから始めた大人向けの鞄や財布も独自店舗での販売を開始しています。
D2Cに移行させることで、それまでは難しかったスピーディーな変革、顧客対応を実現した成功事例です。
男性向け化粧品の地位を獲得:BULK HOMME
東京都渋谷区に本社を構える株式会社バルクオム。同社では、男性のライフスタイルにスキンケアという新しい価値を提供するブランドとして、オンライン定期購入型の男性向け化粧品販売を行っています。
同社がD2Cで成功した理由の一つが顧客をマーケティングパートナーとした点です。顧客がSNSに投稿した自社商品の画像を広告クリエイティブに活用。
ユーザー視点による自社商品を利用する画像は通常の広告よりもリアリティを持って顧客に伝わるため、高い広告効果が発揮されています。
SNSで拡散が成功:Mr. CHEESECAKE
東京都港区にある株式会社Mr.CHEESECAKE。チーズケーキの製造販売を行っている同社では、実店舗を持たずECのみの販売しているのが特徴です。販売数量もごくわずかなうえ、完全受注販売という希少性も相まって高い人気を誇っています。
シェフのこだわりやチーズケーキに対する思いをメッセージとして伝えることで、ストーリー性をつくっているのも人気の要因といえるでしょう。顧客と真摯に向き合う姿勢がD2Cのモデルと合って成功につながっています。
D2Cで成功するためのポイント

ここでは、D2Cブランドで成功するために、3つの観点を押さえましょう。
D2Cに向いた商品設計
D2Cに向いた商品設計は、定期購入や消耗品など継続的に購入される商品が向いています。
明確なUSP(独自の強み)、採算の取れる価格設定といったビジネスモデルの設計が整っています。
特に、化粧品やサプリのような補充需要が見込める商材は、定期配送などで顧客接点を継続でき、LTVの最大化にもつながっています。
また、小規模でのテスト販売やユーザーからのフィードバックを素早く反映し、PDCAを回すことで、新規顧客獲得にも成功しています。
コンセプトとストーリーで世界観を共有する
D2Cブランドは「誰のために、なぜ作られたか」というコンセプトとストーリーが差別化の中核になります。
ECサイトや商品パッケージ、写真・動画、広告に至るまでトーンと表現を統一することで、一貫した世界観を顧客に伝えられます。
創業背景や素材へのこだわり、実際の利用者の声を丁寧に語ることで感情的な共感を生み出し、単なる機能比較ではなく「共感」による選択を促します。
例えば、開封体験や同梱物の演出を工夫し、SNSで共有されやすくすることも有効です。
結果として、ストーリーが自然な拡散とロイヤル顧客化を後押しします。
SNSを軸にした発信とコミュニティ作り
SNSはD2Cの認知拡大とファンかを加速する主要チャネルです。
まずは、ターゲットが実査に利用するプラットフォーム(Instagram、TikTok、YouTube等)を絞り、各フォーマットに合わせた映像や短尺コンテンツを継続的に配信します。
ユーザー生成コンテンツ(UGC)を促すハッシュタグやレビュー誘導、アンバサダープログラムで信頼性を高めていきましょう。
加えて、ライブ配信やQ&A、コミュニティグループで双方向コミュニケーションを育て、SNSで得た反応を商品改善に還元するサイクルを構築することが成功の鍵です。

まとめ

さまざまなメリットを持つD2Cですが、扱う商品や企業カラーによって活かし方は異なります。今回、6つの事例を紹介しましたが、それぞれの企業によってD2Cのやり方が違う点を理解し、自社に合ったやり方を見つけ出しましょう。
D2CはB2Bに比べ顧客に近づけるメリットがありますが、その分、対応の手間は確実に増加します。
そこでおすすめなのが接客の効率化であり、それを実現するのがチャット型Web接客プラットフォーム「GENIEE CHAT」です。
「チャットEFO」という新しい手法でECの売上向上、サイト運営効率化を実現します。ECサイト運営でお悩みの際は、ビュースルーコンバージョンの設定に加え、「チャットEFO」の機能や事例などを紹介する資料をダウンロ―ドしてみてください。
チャット型EFOツール「GENIEE CHAT」
株式会社ジーニーでは、入力フォームを改善し、コンバージョン率を向上させるための「GENIEE CHAT」を提供しています。
Webサイト上に設置している入力フォームをチャット型に置き換えることで、スムーズなフォーム入力が可能になり、その結果、フォーム離脱率を低減し、入力完了率の向上が期待できます。

資料ダウンロードはこちら
関連記事
-

-

-
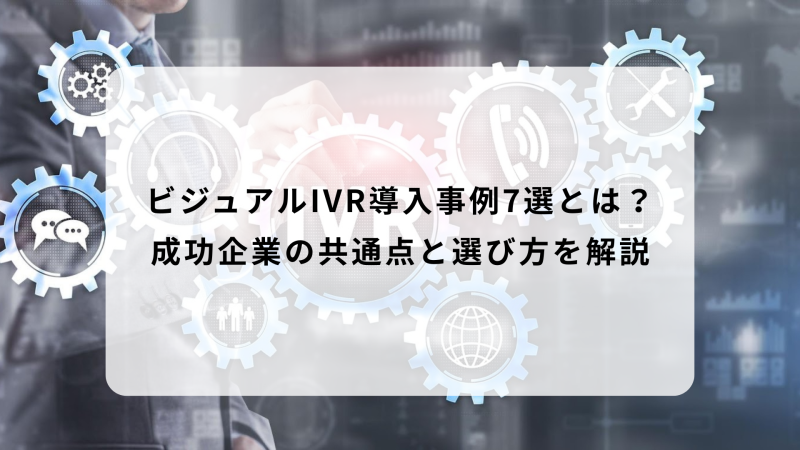
-

-
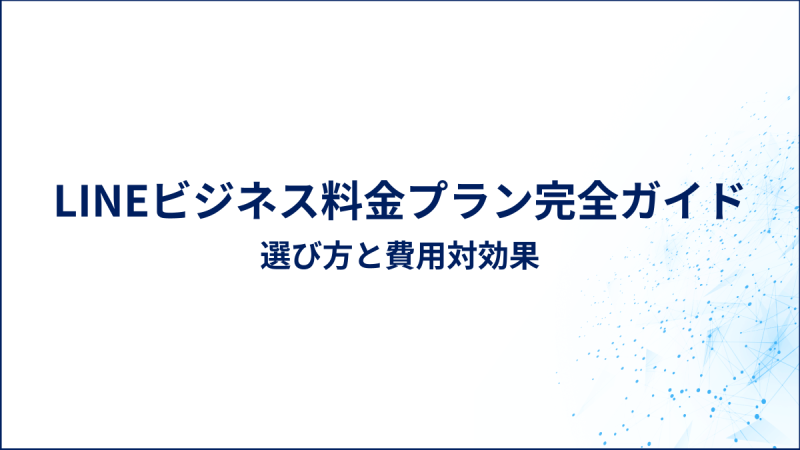
-
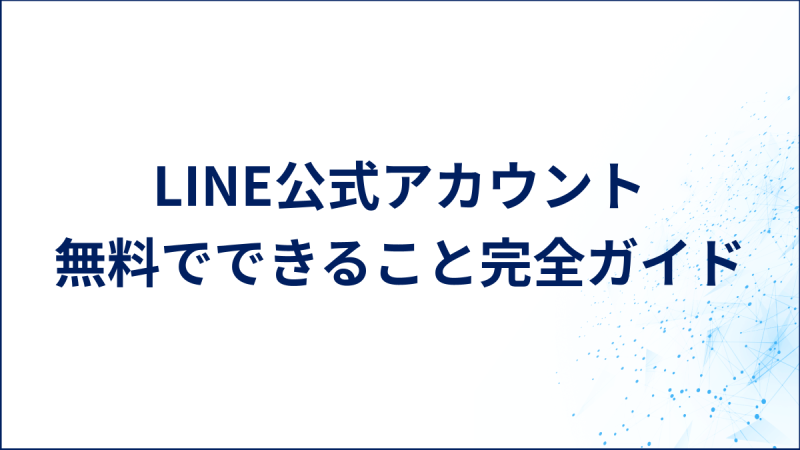
-

-