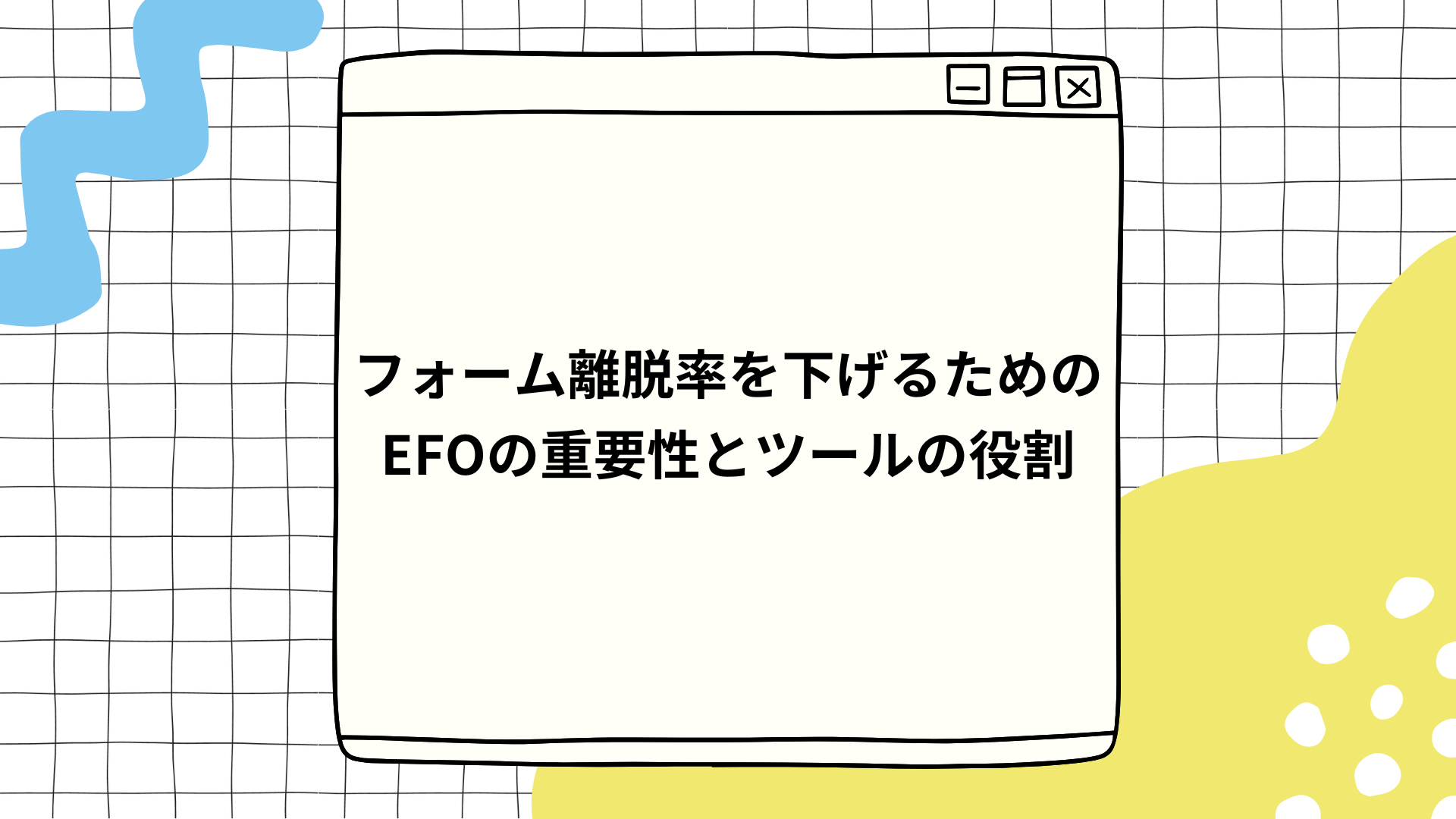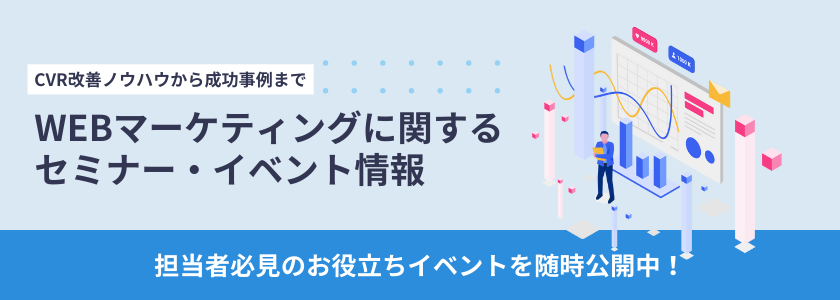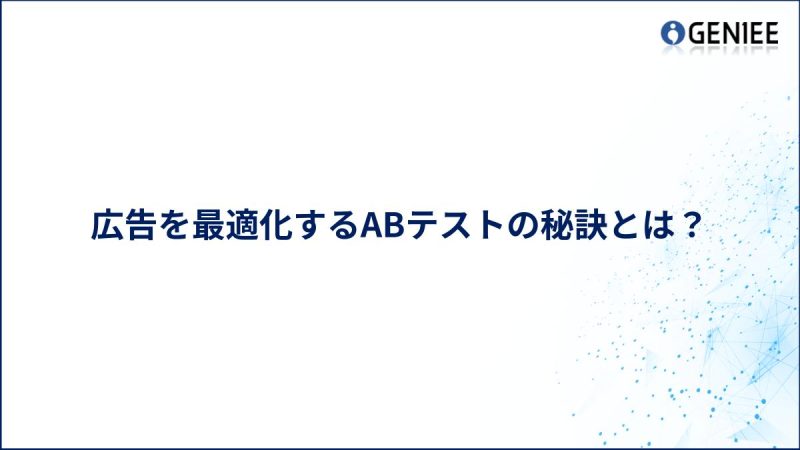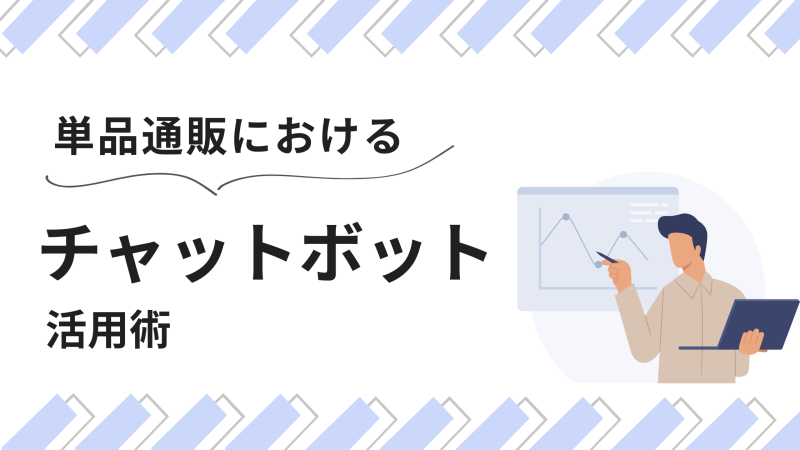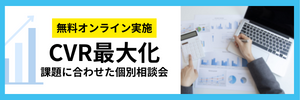Webサイトへの流入はあるものの、コンバージョンにつながらない。その最大の要因は「入力フォーム」での離脱です。実際、フォーム入力開始後に6〜7割のユーザーが離脱すると言われています。そのため、改善の余地は非常に大きいとされています。
そんな中、注目されているのが「EFO(Entry Form Optimization)」です。過剰な項目数やエラー時の混乱、スマホでの操作性の悪さなどを解消することで、離脱率を大幅に抑制できます 。
さらに、EFOツールの導入によって、ノーコーディングでのABテスト実装やエントリーフォームの最適化が可能になります。エラー箇所の可視化、フリガナ・住所補完、自動切替など具体的機能で離脱防止につながります。また、チャット形式に置き換えて会話形式で入力を促す「チャット型EFO」も、ユーザーへのストレス軽減や高い完了率向上に寄与しています。
本記事では、広告やSEOで獲得した流入を最大限いかすために、EFOの重要性とツールを活用することでどのような成果が得られるのかを解説していきます。
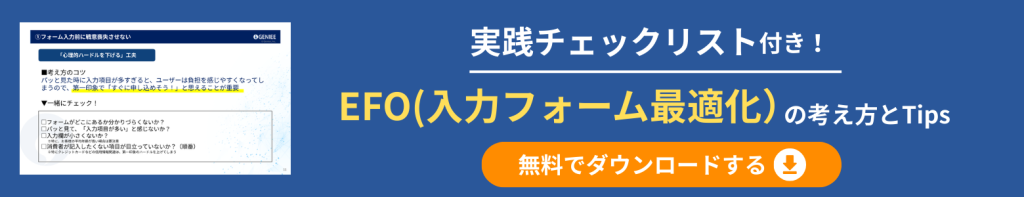
目次
なぜ「フォーム離脱率」対策が重要なのか?

「広告やSEOでしっかりと流入が取れているのに、思ったような成果につながらない。」そのような課題に直面しているなら、原因は「入力フォームでの離脱」にあるかもしれません。
せっかく広告など、コストをかけて集めた見込み客を、最後の最後で取りこぼしている可能性があるのです。しかもこの取りこぼしは、アクセス解析ツールでは気づきにくいです。つまり、マーケティングの盲点になりがちです。放置すればCVRの改善は頭打ちになり、広告投資の回収効率も悪化していきます。
どんなに優れた集客施策も、フォームでの離脱が多ければ成果につながりません。だからこそ、フォーム離脱率の改善は、CVR向上と費用対効果の最大化に直結する「最も効果的な一手」なのです。
フォーム離脱率が高いと、どれほどの損失が出るのか?

フォーム改善は「後回しにされがち」な領域です。しかし、実は最も大きなインパクトを持つ改善ポイントの一つです。
ここでは、フォーム離脱によって生じている見えにくい損失について、整理してみましょう。
見込み客の約7割が離脱している現実
Webフォームの離脱率は、一般的に60〜70%程度と言われています。
つまり、100人が入力を開始しても、最終的にコンバージョンするのはわずか30〜40人ほどです。裏を返せば、60人以上が途中で離脱してしまっているのです。
この数字は、業界やフォームの長さによっても変動します。しかし、どの業界でも一定の離脱は避けられないのが現実です。だからこそ、少しでも離脱を減らす工夫が求められます。
広告費や集客コストがムダになっている可能性
仮に月100万円の広告費をかけて1,000件の流入を得たとしましょう。そのうち500人がフォームに到達し、70%が離脱した場合、350人の見込み客を取りこぼしていることになります。
つまり、広告費のうち35万円分に相当する流入がコンバージョンせずに離脱していると考えると、その損失の大きさが想像できます。
さらに、離脱の要因が「フォームの使いづらさ」だったとすれば、それは改善可能な機会損失です。
原因を誤認しやすく、対策を誤るリスクも
CVが上がらない場合、多くの企業は「集客数が足りない」「広告が悪い」と考えがちです。
しかし、実際にはフォームでの離脱がボトルネックになっているケースも少なくありません。
この誤認が続くと、間違った打ち手(広告費の増額、サイト全体の改修など)にリソースを割き、非効率なマーケティングに陥ってしまうリスクがあります。
だからこそ、今一度「フォーム離脱率」を可視化し、改善に向けたアクションを取ることが、マーケティング全体の成果に直結するのです。
フォーム離脱が起きる主な原因

入力フォームは、ユーザーにとって「あと一歩で完了」の場面でありながら、離脱が発生しやすいポイントでもあります。
ここでは、フォーム離脱を引き起こす主な要因を整理してみましょう。
①入力項目が多すぎて、うんざり・・
フォームに必要以上の項目があると、入力負荷が高くなり、離脱を招く大きな要因になります。
特にスマートフォンからアクセスするユーザーにとっては、10項目を超えるフォームは心理的ハードルが高く、「時間がかかりそう」「面倒」と感じて離脱してしまうケースが多くあります。
②エラー表示がわかりづらい
入力ミスがあった場合に、どこをどう直せばよいかがわかりにくいフォームは、ユーザーに強いストレスを与えます。
「なぜ送信できないのか分からない」「もう一度最初から入力する必要がある」といった状況では、離脱の確率が一気に高まります。
③スマホでの操作性が良くない
フォームはPCだけでなく、スマホユーザーの体験も重視する必要があります。
項目が詰まっていて見にくい、キーボードの切り替えが多い、誤タップが起きやすいといったフォームは、途中で面倒になって離脱されやすいです。
④「どれだけ時間がかかるか分からない」不安
見やすさ、わかりやすさ、入力のしやすさによって離脱率は大きく変わります。
フォームの記入欄が小さくてスマホからだとクリックがしづらい、文字が見づらいなど、ユーザーがストレスを感じやすいフォームデザインは離脱率が高くなります。
また、「送信」や「次へ進む」のような次のステップへの誘導をするボタンも、他のボタンとあまり違いがないデザインだと、ユーザーが見落とす、もしくは記入の途中で誤って押してしまうなどのエラーを起こしやすく、ユーザーの離脱要因です。
そして、これらの問題を解決するために行われる対策をEFO(EFO対策)といいます。
⑤フォームの存在に気づかない・動線が良くない
そもそも、ユーザーがフォームにたどり着けていない場合もあります。
「CTAやリンクが目立たない」「ページの下部に隠れている」「別ページへの遷移に違和感がある」といった、動線の悪さも、フォーム離脱以前の課題として見落とされがちです。
フォーム離脱を防ぐ改善策とEFOの重要性

ここまでご紹介したように、フォームでの離脱は「最後の取りこぼし」ともいえる重要なポイントです。この課題を解消するために注目されているのが、「EFO(Entry Form Optimization:入力フォーム最適化)」です。
ここでは、具体的な改善策とともに、EFOの役割をご紹介します。
EFOとは?入力フォームでのストレスを減らす手法
EFOとは、ユーザーがフォームに入力しやすくなるように最適化する取り組みのことです。
単なるデザイン変更ではなく、UX(ユーザー体験)を向上させ、入力のストレスを減らすための改善手法です。
たとえば以下のような施策がEFOに含まれます。
- 入力項目の見直し(不要な質問の削減)
- リアルタイムエラー表示
- 住所・フリガナなどの自動補完
- 入力途中の離脱防止ポップアップ
- スマホ最適化(タップしやすいUI、文字サイズ調整)
これらの改善により、フォームの完了率(CVR)が大幅に向上するケースも多く報告されています。
▼関連記事:CVR改善で売上を上げる7つの実践施策|BtoCサイト担当者必見
EFOツールを使えば、施策実行がスムーズに
EFOは効果が見込める一方で、「社内で改修するには時間も工数も足りない…」という声も多くあります。そこでおすすめなのが、EFO専用ツールの導入です。ツールを活用すれば、次のような利点があります。
- ノーコードでEFO施策が実装できる
- リアルタイムでABテストや改善効果を検証できる
- ユーザーの離脱ポイントをデータで可視化できる
また、対話型のEFOツールは「選択式で迷わせない」「質問を1つずつ表示して負荷を下げる」などの仕掛けによって、入力完了率の大幅な改善が期待できます。
▼関連記事:EFO × チャットボットの力でユーザー体験を最適化する方法
EFOツールを使うメリットと選び方のポイント

フォーム離脱対策にはEFOが有効ですが、自社開発や手作業での対応には限界があります。そこで、EFOツールの導入が多くの企業で進んでいます。まずは、ツールを使うメリットと、選び方のポイントを押さえましょう。
導入で得られる即効性と効率化
EFOツールを使えば、ノーコードでスピーディにフォーム改善施策を実装可能です。
これにより、改善策を素早く試せるため、成果が早く実感できるのが大きなメリットです。
また、ツールによってはABテスト機能が標準搭載されており、複数の改善案を比較検証しながら効果を最大化できます。
自社開発との違いと選び方のポイント
自社でフォームを開発・改修する場合、時間やコスト、エンジニアリソースの確保が課題です。一方、EFOツールはパッケージ化されているため、運用負担を大幅に軽減しつつ継続的な改善が可能になります。
選ぶ際は以下をチェックしましょう。
①使いやすさ
EFO対策は、中長期的にフォームのデザインや項目の修正をしていく必要があります。
そのため、自社の担当者が使いこなせるのか?という点がとても大切です。これは、単にシステムとしての機能やUIデザインの問題だけではなく、困った時にすぐサポートしてもらえるのか?問い合わせにすぐ回答してもらえるのか?などのカスタマーサポートの面も考慮しておくと良いでしょう。
②ABテスト機能の有無
ABテスト機能とは、デザインや細かな設定を微妙に変えた複数種類のフォームを出し分けることにより、自社のお客様に本当に最適なフォームがどういうものなのか?を検証ができる機能です。この機能がついていないと、お問い合わせ数が減少したり、頭打ちになった時の改善点がわからなくなったりしてしまうので、必ず確認しましょう。
③汎用性
EFOツールの中には、 チャットボット機能による顧客満足の向上も狙えるものや、ショッピングカートとの連動などができるものなど、EFO対策だけでなく各段階のユーザーへのアプローチが同時に行えるものもあります。1つのツールで自社サイトの様々なウィークポイントも補えるのであれば、汎用性があったほうがより効果的と言えるでしょう。
④料金体制
EFOツールの料金体制には、月額固定のものやお問い合わせ数に応じて成果報酬型で費用が発生するものなど様々です。また、設置時の初期費や、サポートを受けるなら別途見積もりが必要なったりすることもあるので、Webサイトに掲載されている情報だけで判断せず、資料請求やお問い合わせをして比較してみましょう。
まとめ
フォーム離脱率は、見えづらく、見過ごされがちな課題ですが、実はCVR向上・CPA改善に直結する「最後の打ち手」です。
広告やSEOで集客を強化しても、フォームでの離脱が多ければ成果は最大化されません。だからこそ、「フォーム改善=利益改善」につながる重要なアクションとして捉えるべきです。
フォーム改善には多くの方法がありますが、最も手軽に、かつ効果的に着手できるのがEFOツールの活用です。
もし「自社での開発は難しそう」「スピード感をもって改善したい」と思ったら、ツールの導入も検討すると良いでしょう。
フォームの離脱を下げる「GENIEE CHAT」
株式会社ジーニーでは、入力フォームを改善し、離脱率を改善するための「GENIEE CHAT」を提供しています。
Webサイト上に設置している入力フォームをチャット型に置き換えることで、スムーズなフォーム入力が可能になり、その結果、フォーム離脱率を低減し、入力完了率の向上が期待できます。

関連記事
-
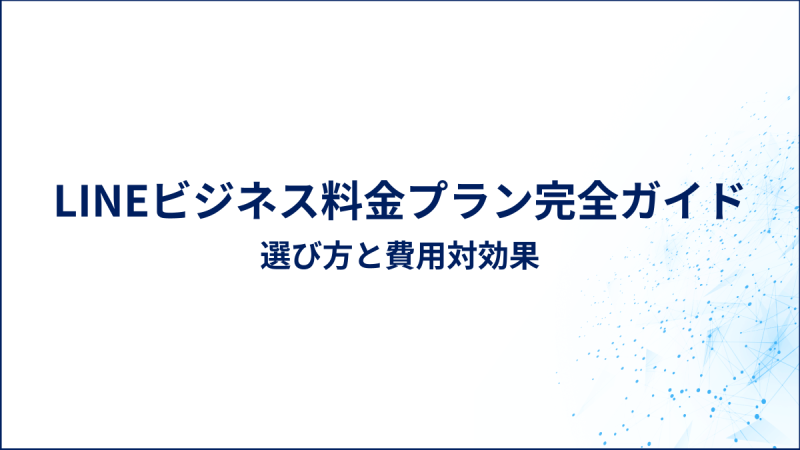
-
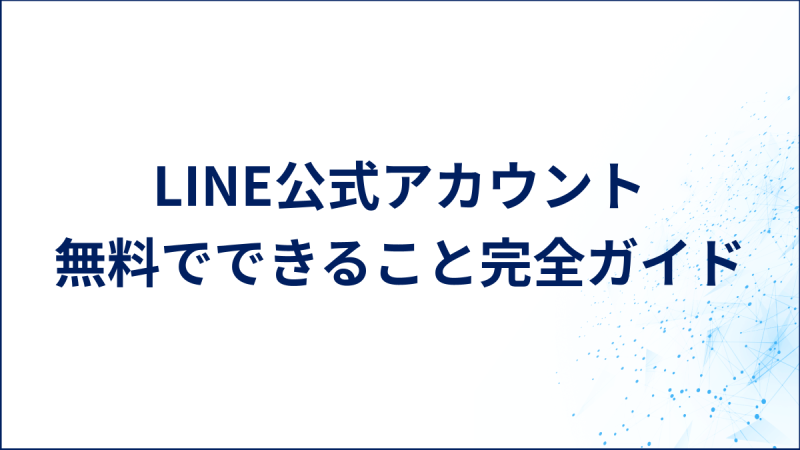
-

-
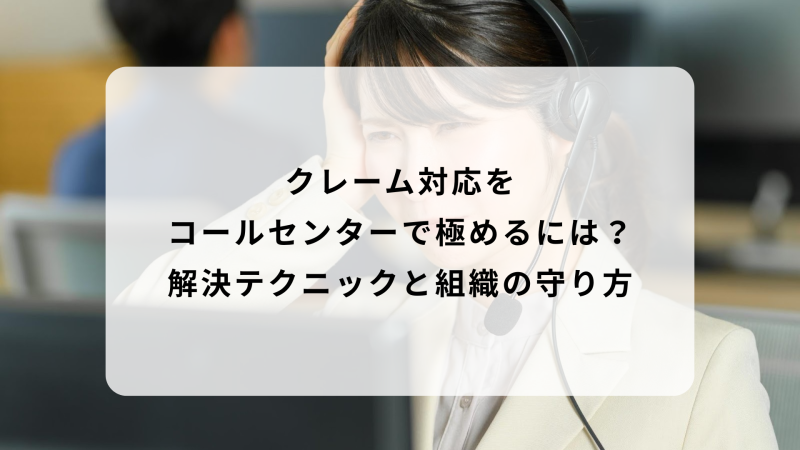
-

-
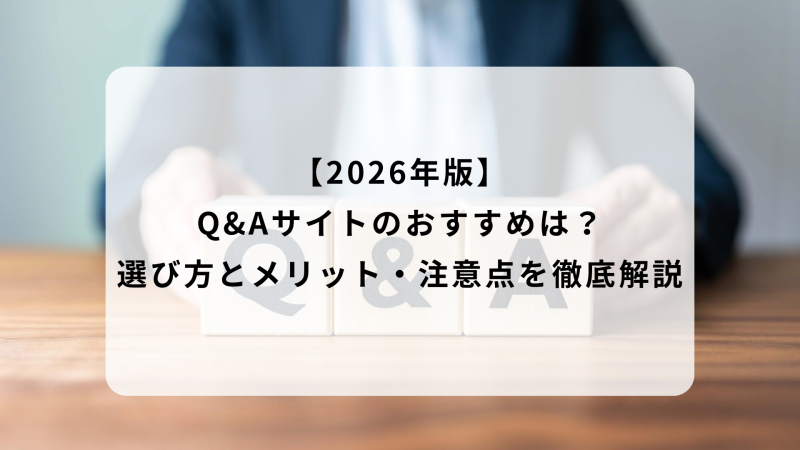
-

-