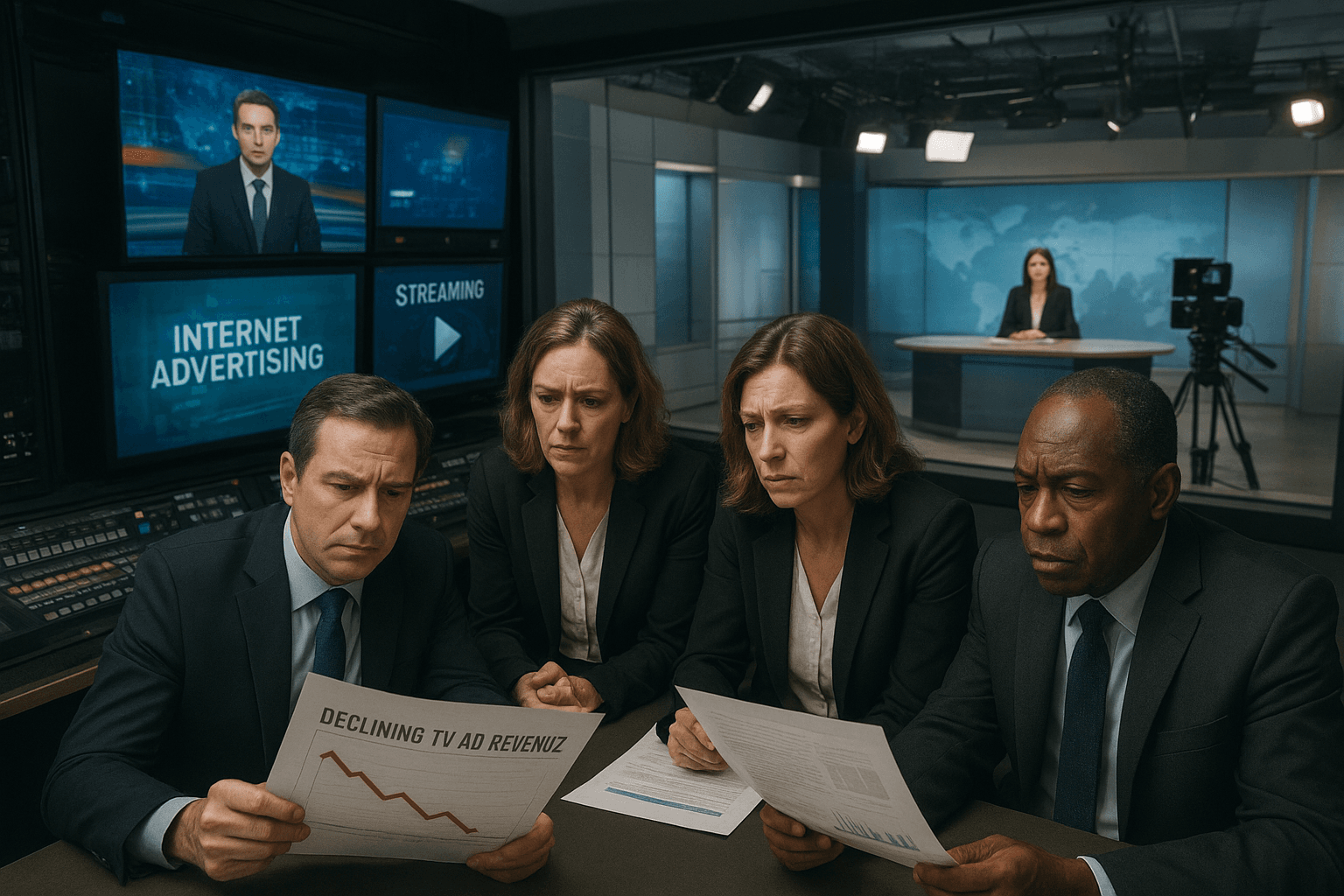顧客セグメンテーションをCDPで高度化|オンライン・オフライン統合で成果最大化

この記事でわかること
- 営業現場では顧客情報の分散、追客優先順位の曖昧さ、無駄なターゲット追求により機会損失が発生している。
- セグメンテーションにより営業リソースの最適配分、成約率向上、顧客満足度向上、オンライン・オフライン統合理解が実現できる。
- 属性、行動データ、心理・価値観、ニーズ・課題の4つの基準で顧客を分類し、それぞれに最適なアプローチを実施する。
- 目的明確化→データ統合→分類基準策定→評価と優先順位付け→実行と検証のPDCAサイクルで段階的に実践する。
- CDPを活用することで、MAやSFAでは捉えきれないオフライン接点(店舗・展示会・電話など)も含めた全接点データの統合セグメンテーションが可能になる。
1. なぜ今、セグメンテーション(顧客分類)が必要なのか

営業現場では、店舗、Web、展示会、電話など多様な接点で日々蓄積される顧客情報を十分に活かしきれていないケースが少なくありません。特に、オンラインとオフラインのデータが分断されていることで、顧客の全体像が見えず、最適なアプローチができていない企業が多く存在します。
営業現場で起きている3つの課題
顧客情報の分散による機会損失
各部門や担当者が個別に顧客情報を管理していると、他部署が持つ貴重な情報を見逃してしまいます。その結果、最適なタイミングでアプローチできず、商機を逃すことになります。
追客の優先順位が曖昧で非効率
すべての見込み客に画一的な対応をしていては、営業リソースが分散します。どの顧客を優先すべきか判断基準が不明確だと、成果につながりにくい顧客に時間を費やすことになります。
無駄なターゲット追求による成約率低下
ニーズが顕在化していない顧客や、自社商材とマッチしない顧客を深追いしても成約には至りません。適切な顧客分類ができていないと、営業効率が大きく低下します。
セグメンテーションとは
セグメンテーション(顧客分類)とは、保有する顧客を特定の基準でグループ化する手法です。属性、行動、ニーズなど、さまざまな切り口で顧客を整理することで、それぞれに最適なアプローチが可能になります。
この手法を活用すれば、限られた営業リソースを効果的に配分し、成果を最大化できます。
2. セグメンテーションがもたらす4つの価値

適切な顧客分類を実施することで、営業活動に以下のような価値をもたらします。
営業リソースの最適配分
顧客を分類し優先順位を明確にすることで、成約可能性の高い顧客に集中できます。IPA(情報処理推進機構)の調査では、データ活用による業務効率化を実現した企業において、営業生産性の向上が報告されています。
出典元:IPA「DX白書2023」https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/dx-2023.html
成約率の向上
顧客のニーズや状況に応じた提案ができるため、成約率が改善します。画一的なアプローチではなく、セグメントごとに最適化された営業活動が展開できます。
顧客満足度の向上
顧客が本当に必要としている情報やサービスを、適切なタイミングで提供できます。これにより、顧客との信頼関係が深まり、長期的な関係構築につながります。
オンライン・オフライン横断での顧客理解
すべての接点データを統合することで、顧客の真のニーズが見えてきます。Webサイトで資料請求した顧客が、その後展示会に来場し、電話で問い合わせをした場合、これらの情報が統合されていなければ、同じ顧客に対して何度も同じ説明を繰り返すことになります。
オンライン・オフラインのデータを統合したセグメンテーションにより、顧客の行動全体を把握し、次に取るべき最適なアクションが明確になります。
3. 効果的なセグメンテーション手法4選

顧客を分類する際には、目的に応じて適切な手法を選択することが重要です。ここでは、代表的な4つの手法を紹介します。
【画像2:4つのセグメント手法の比較図】
セグメンテーション手法比較表
| 手法 | 分類基準 | 特徴 | メリット | 活用場面 |
| 属性(デモグラフィック)セグメント | 年齢、性別、居住地域、企業規模、業種など | 最も基本的で取り組みやすい | ・既存データから即座に分類可能・大まかな傾向把握に有効・導入ハードルが低い | 初期セグメント設定、基本的なターゲティング |
| 行動データセグメント | 購買履歴、Web閲覧履歴、問い合わせ履歴など | 顧客の実際の行動に基づく | ・関心度や購買意欲を可視化・タイミングを逃さない・リピート予測が可能 | 追客優先順位付け、リピート施策 |
| 心理・価値観(サイコグラフィック)セグメント | ライフスタイル、価値観、興味関心など | 顧客の内面的要素で分類 | ・深い顧客理解が可能・感情訴求に有効・ブランディング連動 | メッセージ設計、ブランド戦略 |
| ニーズ・課題セグメント | 抱える課題、求める解決策など | 本質的なニーズに基づく | ・提案精度が高まる・本質的ニーズに対応・競合との差別化 | ソリューション提案、コンサル営業 |
具体例:BtoC・BtoB比較
| 分類基準 | BtoC(個人向け)具体例 | BtoB(法人向け)具体例 |
| 属性セグメント | 20代女性、都市部在住、年収400万円以上 | 製造業、従業員100名以上、関東エリア |
| 行動セグメント | 月3回以上サイト訪問、カート放棄経験あり | 資料ダウンロード済み、価格ページ閲覧複数回 |
| 心理セグメント | 環境意識が高い、品質重視、新しいもの好き | 革新志向、コスト重視、安定性重視 |
| ニーズセグメント | 時短したい、健康改善したい、スキルアップしたい | 業務効率化、売上拡大、人材不足解消 |
BtoC・BtoB特性比較表
| 項目 | BtoC(個人向け) | BtoB(法人向け) |
| 決裁プロセス | 個人判断(即決可能) | 複数人関与(稟議・承認必要) |
| 検討期間 | 短期(数日〜数週間) | 長期(数週間〜数ヶ月) |
| 購買動機 | 感情的要素が強い | 論理的・合理的判断 |
| 重視ポイント | 価格、デザイン、利便性 | ROI、導入効果、サポート体制 |
| 情報収集 | SNS、口コミ、広告 | 展示会、ホワイトペーパー、事例 |
それぞれの特性を理解した上で、自社に適したセグメント基準を設定することが成功の鍵となります。
4. セグメンテーション実践の5ステップ

実際にセグメンテーションを導入する際は、以下のステップで進めることをおすすめします。
【画像3:セグメンテーション実践5ステップのフロー図】
ステップ1:目的を明確にする
まず、何のために顧客を分類するのか、目的を定めます。
- 新規顧客獲得の効率化
- 既存顧客の育成強化
- 休眠顧客の掘り起こし
目的が曖昧だと、適切な分類基準を設定できません。
ステップ2:データを統合する
社内に散在する顧客情報を一箇所に集約します。
- 営業部門が持つ商談情報
- マーケティング部門が持つ反応データ
- カスタマーサポート部門が持つ問い合わせ履歴
バラバラに管理されていた情報を統合することで、顧客の全体像が見えてきます。
ステップ3:分類基準を策定する
目的に応じて、どのような基準で分類するかを決定します。
- 単一の基準で分類するのか
- 複数の基準を組み合わせるのか
- 何段階のセグメントに分けるのか
実務で運用可能な、シンプルな基準設定が重要です。
ステップ4:評価と優先順位付けを行う
策定した基準に基づき、実際に顧客を分類し、セグメントの有効性を評価します。
4R評価基準:
| 評価項目 | 内容 | 確認ポイント |
| Rank(優先順位) | 市場規模や収益性は十分か | ・セグメントの市場規模・期待収益性・成長可能性 |
| Realistic(実現可能性) | 自社のリソースで対応可能か | ・人員体制・予算・技術力 |
| Reach(到達可能性) | そのセグメントに確実にアプローチできるか | ・接点の有無・コミュニケーション手段・アクセス方法 |
| Response(測定可能性) | 施策の効果を測定できるか | ・KPI設定可能性・データ取得可否・効果測定方法 |
これらの視点で評価することで、注力すべきセグメントが明確になります。
ステップ5:実行と検証を繰り返す
セグメントごとに最適化された施策を実行し、効果を検証します。
- 施策の実施
- 成果の測定
- 改善点の抽出
- セグメント基準の見直し
PDCAサイクルを回すことで、精度が向上していきます。
5. CDP活用でセグメンテーションを高度化

セグメンテーションの効果を最大化するには、CDP(Customer Data Platform:顧客データ基盤)の活用がおすすめです。
CDPとは
CDPとは、社内外に散在する顧客データを統合し、一元管理するためのプラットフォームです。営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、各部門が持つ情報を集約し、顧客一人ひとりの全体像を可視化します。
経済産業省のデジタルガバナンス・コードでも、データ統合基盤の整備が企業のDX推進における重要要素として位置づけられています。
出典元:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html
セグメンテーションにおけるCDPの強み
既存ツールとの違いと連携
多くの企業では、すでにMA(マーケティングオートメーション:マーケティング活動を自動化するツール)、SFA(営業支援システム)、CRM(顧客関係管理システム)などを導入しています。これらのツールも顧客データを扱いますが、CDPとは役割が異なります。
MA・SFA・CRM・CDP機能比較表
| ツール | 主な役割 | 得意なデータ | 主な機能 | セグメンテーション能力 |
| MA | マーケティング施策の実行 | オンライン行動データ | ・メール配信・Web行動追跡・スコアリング | オンラインデータのみでのセグメント |
| SFA | 営業活動の管理 | 商談・案件データ | ・商談管理・案件進捗管理・営業活動記録 | 営業データのみでのセグメント |
| CRM | 顧客関係の維持 | 顧客基本情報・購買履歴 | ・顧客情報管理・購買履歴管理・問い合わせ管理 | 顧客属性・購買データでのセグメント |
| CDP | 全データの統合・配信 | オンライン・オフライン全データ | ・データ統合・ID統合・各ツールへ配信 | 全接点データを統合した高度なセグメント |
MAだけでは捉えきれないオフライン接点
多くの企業が導入しているMA(マーケティングオートメーション)は、Webサイト閲覧、メール開封、資料ダウンロードなど、オンライン上の行動データの取得に優れています。しかし、以下のようなオフライン接点のデータは、MAだけでは統合できません。
| オフライン接点の種類 | MAでの取得 | CDPでの取得 |
| 店舗での購買履歴・接客内容 | ✕ 不可 | ○ 可能 |
| 展示会での名刺交換・商談内容 | ✕ 不可 | ○ 可能 |
| 電話での問い合わせ内容・対応履歴 | ✕ 不可 | ○ 可能 |
| 営業担当者による訪問記録 | ✕ 不可 | ○ 可能 |
| セミナー・イベントへの参加履歴 | △ 一部可能 | ○ 可能 |
CDPは、これらオフラインのタッチポイント情報とオンラインデータを統合し、顧客一人ひとりの全行動履歴に基づいたセグメンテーションを実現します。
例えば、「Webサイトで製品Aのページを3回閲覧し(オンライン)、展示会で製品Aのデモを体験し(オフライン)、その後メールで価格問い合わせをした(オンライン)」という一連の行動を統合して把握できます。
この統合データに基づけば、「製品Aへの関心が非常に高く、価格面で検討中」というセグメントに分類し、価格メリットを訴求する提案を優先的に行うことができます。
リアルタイムなデータ更新
顧客の行動や状況が変化した瞬間に、セグメント情報も自動で更新されます。常に最新の状態で顧客を把握できるため、タイミングを逃しません。
MAやSFAに最新のセグメント情報が即座に反映されることで、適切なタイミングでのアプローチが実現します。
複雑な条件での分類が可能
複数の条件を組み合わせた高度なセグメンテーションが、システム上で簡単に実現できます。手作業では困難だった精緻な分類が可能になります。
例えば、「MAでのメール開封率が高く」「SFAでの商談履歴があり」「CRMでの問い合わせ回数が多い」といった複合条件でのセグメント抽出が瞬時に行えます。
オフライン・オンライン全接点からのセグメンテーション
総務省の情報通信白書によると、顧客接点の多様化が進む中、オンライン・オフライン双方のデータを統合することが、顧客理解の深化に不可欠とされています。
MAでは捉えきれないオフライン接点のデータも、CDPなら統合可能です。以下のような多様なタッチポイント情報を一元管理できます。
オフライン・オンライン接点データ統合表
| 接点タイプ | タッチポイント | 取得データ例 | 連携元システム |
| オフライン接点 | 店舗 | 購買履歴、接客内容、来店頻度 | CRM |
| 展示会 | 名刺交換情報、商談内容、関心製品 | SFA | |
| 電話 | 問い合わせ内容、対応履歴、満足度 | CRM | |
| 営業訪問 | 訪問記録、提案内容、反応 | SFA | |
| セミナー・イベント | 参加履歴、アンケート結果、質問内容 | MA/CRM | |
| オンライン接点 | Webサイト | 閲覧履歴、滞在時間、閲覧ページ | MA |
| メール | 開封率、クリック率、反応時間 | MA | |
| 資料DL | ダウンロード履歴、資料種類、回数 | MA | |
| SNS | 反応、コメント、シェア、いいね | MA | |
| ECサイト | 購買履歴、カート履歴、閲覧商品 | CRM |
これらすべてを統合することで、顧客がどのチャネルで接触しても、一貫した対応が可能になります。さらに、オフラインでの行動とオンラインでの行動を掛け合わせた高度なセグメンテーションが実現します。
出典元:総務省「情報通信白書令和5年版」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/
具体的な活用シーン
BtoC企業の場合
ECサイトでの閲覧商品と実店舗での購買履歴を統合し、顧客の興味関心を正確に把握。オンラインで関心を示したが購入に至らなかった商品を、店舗スタッフが提案することで成約率が向上します。
BtoB企業の場合
展示会で獲得した名刺情報、その後のWebサイト閲覧履歴、資料ダウンロード履歴を統合。関心度の高い企業を自動で抽出し、営業担当者が優先的にアプローチすることで、商談化率が改善します。
オフライン・オンライン統合セグメント活用例
| 業界 | 統合データ | セグメント分類 | 実施施策 | 期待効果 |
| 製造業 | ・展示会で名刺交換(オフライン)・製品仕様ページ複数回閲覧(オンライン)・カタログDL(オンライン)・営業訪問したが不在(オフライン) | 「関心度:高」「検討段階:情報収集中」「接触タイミング:再訪問推奨」 | 営業担当者に優先アプローチアラート送信 | 商談化率が大幅に向上 |
| 小売業 | ・実店舗で商品A購入(オフライン)・ECサイトで関連商品B閲覧(オンライン)・カート放棄(オンライン)・メルマガ開封(オンライン) | 「商品Aの購入者」「商品Bへの関心あり」「メール反応良好」 | 商品Bの特別クーポンをメール配信 | クロスセル成功率が向上 |
| 不動産 | ・モデルルーム来場(オフライン)・物件詳細ページ閲覧(オンライン)・資金計画資料DL(オンライン)・電話で問い合わせ(オフライン) | 「購入意欲:高」「検討段階:資金計画中」「接触頻度:高」 | ローン相談会への優先案内 | 成約率・成約スピード向上 |
6. セグメンテーション成功の3原則

セグメンテーションを成功させるには、以下の3つの原則を守ることが重要です。
データ品質を確保する
分類の精度は、元となるデータの品質に左右されます。
| 品質確保施策 | 内容 | 実施頻度 |
| 入力ルールの統一 | 項目定義、入力形式、必須項目の明確化 | 初期設定時・見直し時 |
| データクレンジング | 誤字脱字修正、表記ゆれ統一、不要データ削除 | 月次・四半期 |
| 重複データの排除 | 同一顧客の重複レコード統合 | 週次・月次 |
| データ鮮度管理 | 古いデータの更新・削除 | 月次・四半期 |
質の高いデータがあってこそ、有効なセグメンテーションが実現します。
継続的に改善する
市場環境や顧客ニーズは常に変化します。
- 定期的な効果検証
- セグメント基準の見直し
- 新たな分類軸の追加
一度設定して終わりではなく、継続的に改善を重ねることが大切です。
部門間で連携する
セグメンテーションの効果を最大化するには、組織全体での活用が不可欠です。
- 営業、マーケティング、サポート部門での情報共有
- 共通の顧客理解に基づく施策展開
- 部門を超えたデータ活用
縦割りを排除し、顧客を中心とした組織運営を目指しましょう。
【AI×次世代型CDPツール関連資料】
データ×AIエージェントがなぜ、またどのようにして事業課題を解決するのか?次世代型CDPとは?
7. まとめ

セグメンテーション(顧客分類)は、限られた営業リソースで最大の成果を上げるための有効な手法です。
顧客情報の分散、追客の非効率、成約率の低下といった課題を抱えている企業にとって、適切な顧客分類は営業活動の質を大きく向上させます。
属性、行動、心理、ニーズといった多様な切り口で顧客を理解し、それぞれに最適なアプローチを実施することで、営業効率と成約率の両方を改善できます。
さらに、CDPを活用すれば、オフライン・オンラインのあらゆる顧客接点データを統合し、より精緻なセグメンテーションが可能になります。MAだけでは捉えきれない店舗、展示会、電話、営業訪問などのオフライン接点情報も統合することで、顧客の全体像に基づいた最適なアプローチが実現します。
まずは自社の目的を明確にし、実現可能な範囲から始めてみてください。小さな一歩が、営業成果の大きな変化につながります。
本記事で使用した専門用語集

ITやシステムに詳しくない方でも本記事をご理解いただけるように本記事で使用している主な専門用語を、どなたにも分かりやすく整理しました。ぜひご確認ください。
営業・ビジネス基本用語
セグメンテーション(顧客分類) 顧客を特定の基準でグループ分けすること。属性、行動、ニーズなどの切り口で分類し、それぞれに最適なアプローチを行うための手法
営業リソース 営業活動に使える人員、時間、予算などの経営資源。限られたリソースを効果的に配分することが営業成果の最大化につながる
成約率 商談や提案が実際の契約に至る割合。見込み客100件に対して10件成約すれば成約率10%となる
追客 一度接点を持った見込み客に対して、継続的にアプローチを行い、成約につなげる営業活動
見込み客 将来的に自社の商品やサービスを購入する可能性がある顧客候補
商談化率 問い合わせや資料請求などから、実際の商談に発展する割合
休眠顧客 過去に取引があったが、現在は取引が途絶えている顧客
クロスセル 既存顧客に対して、関連する別の商品やサービスを提案し、購入してもらう販売手法
セグメンテーション関連用語
デモグラフィック(属性)セグメント 年齢、性別、居住地、企業規模など、顧客の基本的な属性情報で分類する手法
サイコグラフィック(心理・価値観)セグメント ライフスタイル、価値観、興味関心など、顧客の内面的な要素で分類する手法
行動データセグメント 購買履歴、Webサイト閲覧履歴、問い合わせ履歴など、顧客の実際の行動に基づいて分類する手法
ニーズ・課題セグメント 顧客が抱える課題や求めている解決策に基づいて分類する手法
4R(評価基準) セグメントの有効性を評価する4つの視点。Rank(優先順位)、Realistic(実現可能性)、Reach(到達可能性)、Response(測定可能性)の頭文字
システム・ツール用語
CDP(Customer Data Platform:顧客データ基盤) 社内外に散在する顧客データを統合し、一元管理するためのプラットフォーム。各部門が持つ情報を集約し、顧客一人ひとりの全体像を可視化する
MA(マーケティングオートメーション) マーケティング活動を自動化するツール。メール配信、Webサイト訪問者の追跡、リード育成などを効率化する。主にオンライン上の顧客行動データの取得に優れている
SFA(営業支援システム) 営業活動を支援するシステム。商談管理、案件進捗管理、営業活動の記録などを一元管理し、営業効率を向上させる
CRM(顧客関係管理システム) 顧客との関係を管理するシステム。顧客情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを記録し、長期的な関係構築を支援する
データクレンジング データベース内の誤りや重複、不要な情報を削除・修正し、データの品質を高める作業
タッチポイント 顧客と企業が接触する接点。店舗、Webサイト、電話、メール、SNS、展示会など、あらゆる接触機会を指す
DX・データ活用用語
DX(デジタルトランスフォーメーション) デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセスを変革し、競争優位性を確立すること
データ統合 複数のシステムや部門に分散している情報を一箇所に集約すること。顧客の全体像を把握するために不可欠
オンライン・オフライン統合 Webサイトやメールなどのオンラインチャネルと、店舗や電話などのオフラインチャネルのデータを統合すること。CDPの最大の強みの一つ
PDCAサイクル Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を繰り返すことで、継続的に業務を改善する手法
リアルタイム更新 データが変化した瞬間に、システム上の情報も即座に更新されること。最新の状態を常に把握できる
BtoC・BtoB用語
BtoC(Business to Consumer) 企業が個人消費者に対して商品やサービスを提供するビジネス形態
BtoB(Business to Business) 企業が他の企業に対して商品やサービスを提供するビジネス形態
稟議 組織内で決裁を得るために、関係部署や上司に順次承認を求める手続き。BtoB取引では複数人の承認が必要なケースが多い
注:この用語集は、記事内で実際に使用されている用語を中心に構成しており、どなたでも理解できるよう平易な言葉で説明しています。記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報はインターネットや各ツールの公式サイトでご確認ください。