お悩み12 「商談の確度について、属人性が大きい」
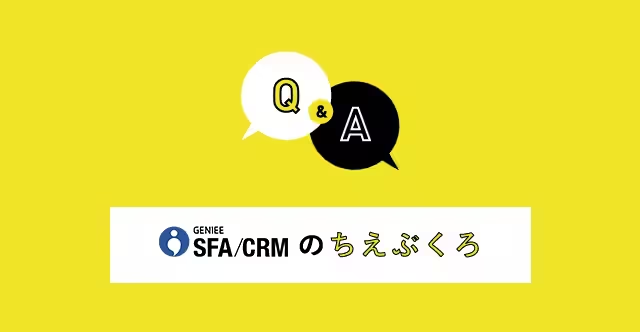
「GENIEE SFA/CRM」のちえぶくろ 悩み12
Q
案件の確度設定についての質問です。各営業メンバーが上げてくる予実報告のギャップが大きく、困っています。メンバーによって受注できるかどうかの見込み(確度)を甘めあるいは辛めに設定する傾向も見え、そうした属人性を排除できればとは思うのですが、良い手が思いつきません。売上目標の達成が非常に困難な状況が慢性化しています。どのような改善方法があるでしょうか?
A
おっしゃる通り、確度設定の基準がきわめて属人的になっているためだと思われます。感覚的に判断することをやめて、確度を切り分けるための別の指標を設定しましょう。それでも担当メンバーによってブレは生じてきますから、定期的な営業会議でコミュニケーションをとり、基準を統一していくことが重要です。
解説
案件確度…「ヨミ」というものは、なかなか厄介なものです。営業グループをまとめるマネージャーからすれば、どれだけの案件がどれほどの確度で動いているかを把握することは重要なことですし、それは経営にも影響する要素です。
一方でその案件が受注できるかどうか、その確実性を測るのは「担当営業の感触」が頼り、という面があるのは否めません。
重要な要素でありながら、担当者の感覚に頼らざるを得ないというのは、どうにも不合理な話です。とはいえ、そのまま放置しておくわけにもいきません。
こんな場合は、まずチーム内で受注確度の基準をつくり、それを共通認識として共有しておくと良いでしょう。たとえば次のような具合です。
確度A 申込書待ち ……………………………………… 受注確率90%以上
確度B 対面の担当者が契約に向けて動いている …… 受注確率60%以上
確度C B以下、50:50の状況 ………………………… 受注確率30%以上
確度D C以下 …………………………………………… ネタ話の領域
「とりあえず」の暫定的なものであっても、こうした基準があればそれを根拠にヨミの配分ができます。あとは定期的な営業会議でコミュニケーションを重ねて、確度A~Dのどこにするかの判断基準をチームとして磨き上げ、統一していけば良いでしょう。
またCRMやSFAを導入していて、すでにある程度のデータの蓄積があれば、過去のデータを分析することで受注・失注の分岐点やその割合を目安として導き出すこともできます。
商談プロセスの段階分けと組み合わせれば、たとえば「商談が担当者だけの段階までだと受注率30%だが、決済責任者も同席の段階に進めば60%の確度Bになる」という判断も可能になるでしょう。
下記のページでは、営業に関するお役立ち資料を公開しております。無料でダウンロードできるので、ぜひお気軽にご活用ください。




























